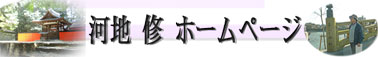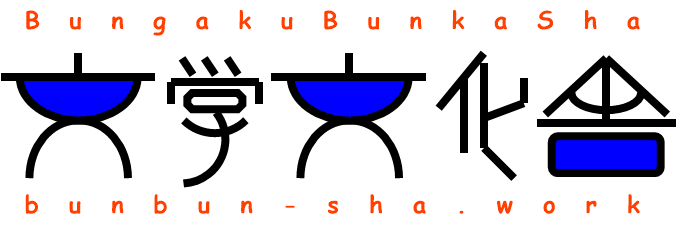-伊勢物語論のための草稿的ノート-
第93回
「ゆく螢雲の上までいぬべくは」―真の「いろごのみ」の物語(45段)(一)
「昔、男」に恋をした「人の娘」
第45段は、ある貴族の娘が、おそらくその屋敷に出入りする「昔、男」に恋をし、その思いが実ることなく、ついに病を得て死に至るという話だが、その娘にはまったく面識がなかった男の、娘の死後の行動までを語る章段である。
美しい純愛の話として、高校の教科書などにもよく掲載される章段なのだが、世の中にはひねくれた人もいるようで、この章段の本来のテーマを捻じ曲げて解釈する研究者もいる。間違って読まれるような難解な話ではないと思うが、『伊勢物語』の名誉のためにも、本章段の要諦を以下書き残しておきたい。まず、本文を掲げる。
昔、男ありけり。人の娘のかしづく、いかでこの男にもの言はむと思ひけり。うちいでむことかたくやありけむ、もの病みになりて、死ぬべき時に、「かくこそ思ひしか」と言ひけるを、親聞きつけて、泣く泣く告げたりければ、まどひ来たりけれど、死にければ、つれづれとこもりをりけり。時は水無月のつごもり、いと暑きころほひに、宵はあそびをりて、夜ふけて、やや涼しき風吹きけり。螢高く飛び上がる、この男、見ふせりて、
ゆく螢雲の上までいぬべくは秋風吹くと雁に告げこせ
暮れがたき夏のひぐらしながむればそのこととなくものぞかなしき
(昔、男がいた。人の娘で親から大切に育てられていたのが、なんとかしてこの男に自分の思いを伝えたいと思ったのだった。そのことを口に出すことが難しかったのであろうか、何かの病を得て、もう死んでしまうという時に、「このように思っていた」と言ったのを、親が聞きつけて、泣く泣く男に告げたところ、男はあわてふためいてやって来たが、娘は死んでしまったので、所在なくそのまま忌に籠っていたのであった。時はちょうど六月の末、大変暑い時節で、宵は音楽を奏し、夜が更けてから、少し涼しい風が吹いたのだった。その時螢が高く飛び上がる、この男はそれを横になって見ていて、
空高く飛んで行く螢よ、雲の上まで行くことができたなら、もうここでは秋の風が吹いていると、雁に伝えここに飛んでくるように言っておくれ
なかなか暮れそうで暮れない長い夏の一日中、ぼんやりと外を眺めていると、特にどのことがということもなく、もの悲しくてならないことよ)
物語の語り出しに、「人の娘のかしづく、いかでこの男にもの言はむと思ひけり」とあるように、この話の端緒は、ヒロインと言っていい「人の娘」の、いわゆる片恋である。中古の物語としては珍しい題材と言うべきだろうが、当時、貴族の邸宅内で、その家に住む婦女子が、訪問した貴公子を垣間見る機会はないわけではなかった。たとえば、『源氏物語』の場合、六条院での夕霧や柏木の蹴鞠を御簾越しに垣間見る女三の宮を思い浮かべることができるが、要は、その邸宅の主人に所用あって訪問する若者が多いのである。
45段は、具体的にどのような階層の貴族の話かは分からないが、上流にせよ、中流にせよ、その家の当主(貴族)である父親が、「人の娘のかしづく」と言うように、自分の娘を大切に養育するのは当然のことであったから、おそらく娘は深窓に育まれていたものと思われる。そういう深窓の娘が、訪問した男を垣間見る機会を得たというのであれば、その「男」は、家の内部にまで入ることが許された若者であったに違いない。
この家の娘は、何らかの関係で頻繁に訪問していた男を見ることになったと思われるが、娘は、自分の恋心を誰にも打ち明けることができなかったのである。少し積極的な娘であれば、たとえば、自身に近しい存在の侍女にでも話すことができたであろう。近しい存在の侍女とは、たとえば「乳母」や「乳母子」ということになるが、それもできないほどの内気な娘ということになる。
娘は、結局「もの病みになりて」ということになったのだが、物が食べられなくなって、やがて衰弱してゆくというケースは、当時はよくあった。物が受け付けられなくなるほど衰弱した場合は、すでに手遅れで、娘は、自身の死に際に最後の力を振り絞って思いを吐露したのである。それを伝え聞いた親(父親である)は、男に「泣く泣く」告げるのであったが、それは「かしづく」娘のことゆえ当然のことであった。
男の行動
物語は、それを聞いた男が、「まどひ来たりけれど」と語っている。中古語の「まどふ」は、現代語の「迷う」とは別の言葉で、理性を失って混乱する意である。つまり、慌てふためいて駆けつける男の様子を表しているが、娘は死去したのであった。その間際、はたして娘と男は話を交わすことができたのかどうか、物語は、そのことにはまるで関心がないかのように、
死にければ、つれづれと籠りをりけり
(娘は死去したので、男は、所在なくそのまま忌に籠っていたのであった。)
と言うのみである。「籠りをりければ」という表現だが、これをどう解釈するかという問題がある。
具体的に言えば、そのまま娘の家に籠ったのか、あるいは男が自宅に帰って籠ったのか、ということになる。事実関係のみで言えば、男は「死穢」に触れたこと(触穢)になるから、自宅に戻って「籠る」とも考えられなくもないが、しかし、この場合、二人に婚姻関係はなかったとしても、亡くなった娘の気持に沿ったかたちで、そのまま娘の家に籠ったとしなければならないのではないか。そのまま自宅に戻ったのでは、なんともあっさりした男の話で、この話がここに、「物語」として採録されるはずがないのである。
文章の流れからしても、
死ぬべき時に、「かくこそ思ひしか」と言ひけるを、親聞きつけて、泣く泣く告げたりければ、まどひ来たりけれど、死にければ、つれづれとこもりをりけり。
と、センテンスが途切れることなく「死にければ、つれづれとこもりをりけり」と進められるのであって、書かれてもいない「男は自宅に帰って」という表現を差し挟んで読むことなどはとてもできないであろう。特に、父親が娘の思いを知り、すぐに男に訴えたところからの男の間髪を入れぬ行動は、娘への愛情にあふれた行動と言うべく、懸命に駆けつけたにもかかわらず死去したとなれば、そのまま娘のために、その家に籠る行動を取ることは自然のことではあるまいか。
つまり、男は、娘の死に臨み、さらにその死に触れて、「夫」としての事後の行動を選択したのであった。娘との婚姻関係はなかったとしても、男の取った行動は、自分のために命を落とした娘の霊を、夫に准ずる立場から慰めようとしたものと思われる。
あえて付加するが、この話を、「こちらの知らぬ間に恋情を持ち、それ故に死んだ女の喪に触れた男の、やり場のないような迷惑な気持」(新潮日本古典集成『伊勢物語』・頭注)などと読むのは、どうにも理解に苦しむところである。
『伊勢物語』という作品が、なぜこの話(45段)をここに掲載したのか、ということを考えなければなるまい。
―この稿続く―
2021.8.1 河地修
一覧へ