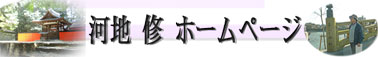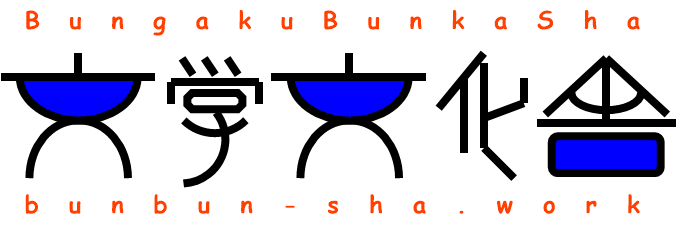-伊勢物語論のための草稿的ノート-
第73回
いにしへのしづのをだまき」―『伊勢物語』「第32段」の基層
義経の物語は、誰もが知っている。悲劇の英雄にふさわしい悲恋もあった。その相手は、白拍子(しらびょうし)の静御前である。側室(妾)ではあったが、義経の逃避行に殉ずるように、晩年は陸奥まで放浪したという伝承もあるが、よくわからない。わかっているのは、鎌倉方に捉えられた後、義経の子を出産、しかし、男児だったために、その子は海に沈められたという話までであろう。
その静御前が、鎌倉で捉えられていた時、頼朝と政子の求めに応じて、鶴岡八幡宮で歌舞を奉納した。都において、天下一の白拍子と謳われた静であったから、満場を圧する程の歌舞であったと言う。その時に詠った歌のなかに、次の歌があった。
しづやしづ しづのをだまき 繰りかへし 昔を今に なすよしもがな
冒頭、己の名に通ずる「しづ」を繰り返しながら、下の句―昔を今になすよしもがな(昔を今とするすべがほしい)と、そこに込めた願いは、言うまでもなく、義経と共有した「昔」を「今」に取り返したい、ということであった。当然、頼朝は激怒したが、政子が取りなしたと言われている。
実は、この歌は、『伊勢物語』「第32段」の和歌の初句だけを言い換えたものである。次に掲げよう。
昔、もの言ひける女に、年ごろありて、
いにしへの しづのをだまき 繰りかへし 昔を今に なすよしもがな
と言へりけれど、なにとも思はずやありけむ。
(昔、逢瀬を持った女に、何年か経って、
古の倭文の苧環を繰り返し同じように何度も回し糸を繰り出すように、私たちの関係も、もう一度あの頃に戻りたいものだ
と言ったけれども、女は何とも思わなかったのであろうか、返事はなかった)
この章段の場合、まず解釈問題として「もの言ふ」の扱いがある。「もの言ふ」は、漠然とした表現ではあるが、場面によって様々な使い方がなされる。ここでは、男女の関係を持つ、ということである。昔そういうつき合いをした女がいたが、どういう事情があったのか、別れたのである。そして、「年ごろありて」―何年かの後に、男が、再び、よりを戻そうと、女に働きかけたものと思われる。
こういうことは、男と女の世界にあっては、よくある話ではあろう。よくある話であるということにおいて、この歌は多くの男女に受け入れられたに違いない。当然、歌だけでも流行してゆくわけで、その結果として、後世、鶴岡八幡宮における静御前の歌舞の場面へと展開していったということになる。
『伊勢物語』の男の歌は、女と生きた過去への未練なのか、あるいは、別れた女への軽い遊び心の誘いなのか、詳しいことはわからないが、静御前の歌は、しづやしづ、の詠い出しから、義経を慕う悲痛な叫びを聞くようであって、詠歌からは哀切極まる心情が溢れて来る。
ともかく、静御前の歌は、『伊勢物語』「第32段」の歌をその源泉とするのだが、実は、その歌は、元は『古今和歌集』「巻十七」「雑上」「題知らず/詠み人知らず」の歌であったと思われる。しかし、当該歌は、次に掲げるとおり、下句が異なっているのである。
いにしへの 倭文(しづ)の苧環(をだまき) いやしきも よきも盛りは ありしものなり
(身分が卑しい人間も、最高の身分の人間も、今はみな老いを迎えているが、かつては、盛りの時期はあったものであるよ)
『古今集』の「雑歌」とは、「春夏秋冬にも入らぬくさぐさの歌」(仮名序)ということであって、特に決まったテーマで採歌されているわけではないが、当該歌の前後には、「老い」を意識した歌が多く配列されている。たとえば、前後の和歌は次のとおりである。
いにしへの 野中の清水 ぬるけれど もとの心を 知る人ぞ汲む
(昔の野中の清水は、今はぬるいけれども、昔の冷たい清水のことを知っている人は、今も汲みに来る―それと同様、昔の私のことを覚えていてくれる人は、今も会いに来てくれることだ)
今こそあれ われも昔は をとこ山 さかゆく時も あり来しものを
(今でこそ私は歳を取っているが、それでも昔は、男盛りの時もあったものだよ)
この二首の歌に挟まれた当該歌は、あきらかに、人間誰もが老いを迎えるものとの認識を示したものと言っていいが、初句、二句の「いにしへの倭文の苧環」を序詞として「賤しき」を導き出している点が注目される。
この「いにしへの倭文の苧環」とは、この国伝来の機織りの道具の一つであって、まさに、名もなき庶民たちの生活の現場そのものの風景と言っていい。その貧しい「倭文の苧環」の印象から「賤し」を導き出す序詞になるのであるが、歌は、その「賤しき」(賤しい身分の者)も、反対の「よき」(高貴な身分の者)も、みんな歳は取る、しかし、いずれも「盛り」はたしかにあったのだ、という感慨を詠ったのである。
これが、おもしろい歌かどうか、ということになれば、人生の当然の哲理を詠っただけのことで、さほど面白味があるとは思えないだろう。ただ、派手な面白味には欠けるものの、人生において、人間誰もが思い至る実感である以上、当時多くの人に受け入れられた歌ではなかったかと思われる。
そして、この歌を、大きく作り替えたものとして、『伊勢物語』「第32段」があるのである。その最初の実践者が32段の「昔、男」であったかどうかの確証はないものの、ともかく、男は、『古今集』の歌の序詞である「いにしへの倭文の苧環」に着目し、それが「繰り返す」動作を有するところから第三句に「繰り返し」と続け、さらに「昔を今になすよしもがな」と詠嘆したのであった。言うなれば、何の変哲のない「老い」の歌から、別れはしたものの、もう一度あの頃に帰りたい、という「恋」の歌への変貌、もしくは再生ということが行われたと言うことができよう。
『古今集』の「老い」の歌であれ、また『伊勢物語』の「恋」の歌であれ、その詠嘆が「いにしへの倭文の苧環」からもたらされたものであるということは、この国の「うた」というものが、本来どのようなところで詠い継がれてきたものであったかということを示唆するものでもあろう。それは、けっして最上流の貴族社会ではなく、むしろ、社会の底辺で生きてゆかざるを得ない弱者たちの世界がふさわしいものであったかも知れない。
「いにしへの倭文の苧環」は、『古今集』の「詠み人知らず」の「老い」の歌を作り出し、そして、それは『伊勢物語』「32段」においては、あらたに「恋歌」を紡ぎ出し、さらに後世では、失われた愛する人(義経)との「昔」を取り戻したいという究極の弱者でもある静御前の悲痛極まる絶唱を誕生せしめたのであった。この国の「うた」をめぐる見事な歴史の流れを目の当たりにすることができる、と言うほかはない。
2018.2.23 河地修
一覧へ