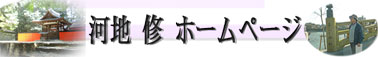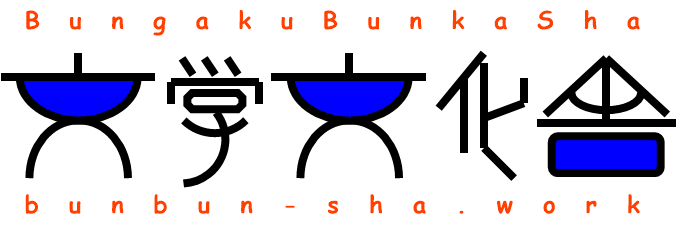-源氏物語講話-
第36回
「巻名」を考える(五)―「夕顔」
「夕顔(ゆふがほ)」という言葉
「夕顔」という言葉は、いつ頃から用いられていたのであろうか。むろん大和言葉であるから、それなりに古いものとは思うが、しかしながら、『萬葉集』、『古今和歌集』には、「夕顔」という語彙は表れてこないのである。これは、当時和歌で詠われなかっただけのことと思うが、それは、その名のとおり、日没後に咲く花だったからであろう。つまり、目に触れない、という意味において、身近な花ではなかったものと思われる。
そもそも「夕顔」は、「ユウガオ」とカタカナで表記する方が、イメージとしてはふさわしい植物であった。その実は、今日でも「干瓢(かんぴょう)」として食用するが、まさに、花より実、という植物であったのである。
「夕顔」という言葉が文献で確認できる初出は、『枕草子』ということになろう。あるいは、「夕顔」に初めて注目した人物が、文献上、清少納言であった、という言い方ができるかもしれない。
夕顔(ゆふがほ)は、花のかたちも朝顔(あさがほ)に似て、言ひ続けたるに、いとをかしかりぬべき花の姿に、実の有様(ありさま)こそ、いとくちをしけれ。などて、さはた生(お)ひいでけむ。ぬかづきといふもののやうにだにあれかし。されど、なほ、夕顔といふ名ばかりは、をかし。
(夕顔は、花のかたちも朝顔に似て、朝顔、夕顔と言い続けてみると、とても風情があるに違いないような花の趣きなのに、その実の格好が、なんとも残念な限りだ。どうして、あんな不格好な実が成ることになったのであろうか。せめて酸漿という物の実ぐらいであってほしいものだ。けれども、やはり、夕顔という名前だけは、素敵だ。)
清少納言『枕草子』「草の花は」
『枕草子』の正確な成立年とその成立事情は定かではないが、少なくとも、『源氏物語』より古いのは確かなことである。「夕顔(ユウガオ)」という植物の存在は、実が食用である以上、『枕草子』以前から当時の人々に知られていたであろうが、それについての随想を、清少納言が初めて文章にしたということになる。そして、その後、紫式部が、『源氏物語』の四番目の巻の名称に用いた、ということになるのである。
この『源氏物語』は、藤原彰子に読まれるべく制作されたものであることは言うまでもないが、さらに言えば、その際、彰子に音読して差し上げた女房たちこそ、実際には最初の読者であったことは間違いない。その女房たちはともかく、はたして、彰子は、この「夕顔(ユウガオ)」という植物の存在を知っていたかどうか―。

夕顔の花は日没後に咲く
「夕顔(ゆふがほ)」を巻名に用いる
後世における『源氏物語』の読者は、「夕顔(ユウガオ)」の実態には、意外と無頓着なところがあるのではあるまいか。『源氏物語』の巻名に使用された時点から、その語彙は、たとえそれがどのようなものであっても、典雅な輝きを放つものであるからだ。
しかし、我々は、この物語を正しく読むために、あくまでも第一次の読者の視点に立たねばならない。彰子にとって、あるいは、彰子の女房たちにとっても、この巻名の「夕顔」という言葉は、一種の驚きをもって受け入れられることになったのではあるまいか。
前述したように、おそらく、彰子はこの「夕顔」と呼ばれる花の存在を知らなかったに相違ない。彰子は、藤原道長の長女であるが、母は左大臣源雅信の女の倫子であったから、その出自は高く、彰子が生まれ育った環境に、「夕顔(ユウガオ)」という植物があったとは思われないのである。「夕顔」巻頭近く、光源氏が隣家の垣根に咲く白い花を、あれは何か、と尋ね、御随身が、
かの白く咲けるをなむ、夕顔と申しはべる
(あの白く咲いているのを、夕顔と申します)
と答えるのは、最上流の貴族階層にとって、この花の存在がほとんど知られていなかったことを物語っている。そして、さらに言えば、上記の言葉に引き続いて、御随身が、
花の名は人めきて、かうあやしき垣根になむ、咲きはべりける
(花の名はまるで人のようで、しかし、このような卑しい界隈の垣根に咲くのでございます)
との解説を行うのは、むろん、物語中の源氏に対するものではあるが、同時に、この物語に聞き入っている彰子への説明も兼ねていたに違いない。
巻名提示の段階で、彰子はともかく、その女房たちは、この巻の物語が、少なくとも、その舞台を、夕顔の花咲く「あやしき」世界となることを予想したことであろう。そのイメージは、「帚木」と同質のものがあるのであり、「帚木三帖」を締め括るにふさわしい巻名であったと言っていい。
『枕草子』と「夕顔」巻
ところで、「夕顔」という言葉の初出である『枕草子』だが、紫式部は、これを読んでいたか、あるいはその内容について、ある程度把握していたのではないかと思われる節がある。それは、清少納言『枕草子』の、「夕顔(ゆふがほ)は、花のかたちも朝顔(あさがほ)に似て、言ひ続けたるに、いとをかしかりぬべき花の姿」(夕顔は、花のかたちも朝顔に似て、朝顔、夕顔と言い続けてみると、とても風情があるに違いないような花の趣き)とある箇所で、ここには、「夕顔」と「朝顔」との積極的な対照があると言っていい。
実は、紫式部もまた、「夕顔」巻において、積極的に「夕顔」と「朝顔」との対照を試みているのである。それは、「夕顔の花咲く宿の女」と「六条わたりの女君」(六条御息所である)との対照である。そもそも、光源氏が夕顔と遭遇することになったのは、「六条わたりの御忍びありき」の「中宿(なかやどり)」として、乳母がいる五条の家を訪ねたのが端緒であった。したがって、「夕顔」巻において、源氏が「六条わたり」の女君を訪ねる場面が登場するのは自然の流れであったが、源氏が、女君のもとで一夜を共にした翌朝、帰ろうとする場面で、件の「朝顔」が登場するのである。源氏は、庭に咲く朝顔の花を見て、女房「中将のおもと」に、次の歌を詠み掛ける。
咲く花にうつるてふ名はつつめども折らで過ぎ憂き今朝の朝顔
(目の前に咲く花を見ながら、移るという言葉は心変わりのようで慎まれるものだが、我がものとせずにはおられない今朝の朝顔のように美しいそなたであることだ)
詠い掛けた相手が女房の「中将のおもと」であることなど、色好みにふさわしい源氏の行動と言うべきだが、彼女は、源氏からの誘いに対して、あえて「おほやけごと」(主人のこと)として、返歌した。
朝霧の晴れ間も待たぬけしきにて花に心をとめぬとぞ見る
(朝霧が晴れて、前栽の花がはっきりと見える晴れ間をお待ちにならず、もうお帰りになろうとされるご様子は、わが宿の花―女君にお心をお留めなさらぬものと思われます)
「中将のおもと」は、源氏の「折らで過ぎ憂き今朝の朝顔」という歌句に対して、「花に心をとめぬとぞ見る」と返したもので、源氏が自分を「朝顔」に擬えて詠いかけたのに対して、「花」―我が主人に心を留めていない、と抗議した。つまり、中将は、間接的に「朝顔」に、主人である六条御息所を擬えたことになるのである。それは、巻の後半、夕顔の死に関わると読める魔性の女の出現にも結び付く「夕顔」と「朝顔」との際立つ対照でもあった。
なお、この「夕顔」巻をめぐる『枕草子』との関係については、すでに清水好子氏が一文を草しておられる(「紫式部と清少納言」『鑑賞日本古典文学枕草子』)。重大な問題提起であり、このことについては、別稿を用意したいと思う。