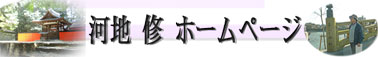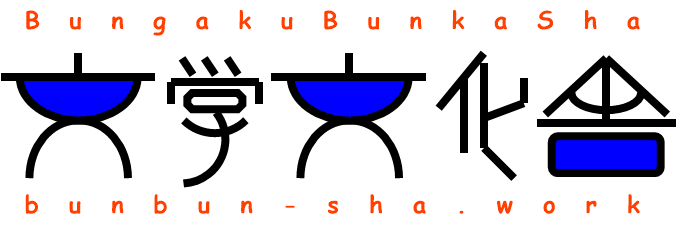-源氏物語講話-
第25回
「巻名」を考える(二)―「帚木」
「帚木(ははきぎ)」という言葉
「帚木」巻の巻名については、多くの注釈が、巻末の源氏と空蟬の歌を指摘する。けっして間違いということではないのだが、はたしてそういった指摘だけで、この物語を正しく読むことになるのかどうか、ということを考えてみたい。
これは言葉の問題なのである。「帚木(ははきぎ)」という言葉が巻名として提示されたとき、この物語の第一次の読者たち(彰子に仕える紫式部の同僚の女房)は、はたしてどう読み取ったか、ということを考えなくてはならない。つまり、首巻の「桐壺」と同様、彼女たちには、「帚木」という言葉に関する、ある共有する概念があったに違いないのである。当たり前のことだが、それが言葉というものであり、その言葉が特殊なものであれば、その共有する概念はより強固に確立していたに違いない。
『日本国語大辞典』は、この語について、次のように解説する。
1、「ほうきぎ(箒木)」に同じ。≪季・夏≫
※元良親王集(943頃か)「ははきぎをまたすみがまにこりくべてたえしけぶりのそらにたつなは」
2、信濃国(長野県)園原にあって、遠くからはほうきを立てたように見えるが近寄ると見えなくなるという伝説上の樹木。転じて、情けがあるように見えて、実のないこと、姿は見えるのに会えないこと、また見え隠れすることなどのたとえ。
※古今六帖-五・雑 思 「その原やふせやに生ふるははきぎのありとて行けどあはぬ君哉」
(以下省略)
(省略したが、この語彙の解説の最後に「『源氏物語』第二帖の巻名」という項目が掲げられている。むろん『源氏物語』の「第一次の読者たち」にとって、このことは「帚木」巻成立の時点ではまだ共有するところの概念とはなっていなかった。「第一次の読者たち」にとっては、たんに(1、)の「箒木」という樹木の謂いか、(2、)の和歌に関する知識ということになるであろう。ここでは、(2、)に掲げられる「古今六帖-五・雑 思」の一首に注目しなければならない。つまり、「第一次の読者たち」は、「帚木」という言葉から、間違いなく「古今六帖」の当該の一首を思い浮かべたのではあるまいか。あるいは、思い浮かべた読者が何人かいたことで、多くの人々(女房たち)の覚醒するところとなったに違いない。
「帚木」が導く世界―ありとて行けど逢はぬ君かな
諸注が指摘するように、「帚木」巻末の光源氏と空蟬による和歌のやり取りは、明らかにこの「古今六帖」の歌に基づいている。こうした詠歌づくりがなされることじたい、前提として、当時の「第一次の読者たち」に当該歌に関する共通の知識があったことがわかるのである。次に、「古今六帖」の和歌とともに、三首を並べて掲げてみよう。
そのはらやふせやに生ふる帚木のありとて行けどあはぬ君かな(古今六帖)
(園原の伏屋に生えている帚木のように、そこにあるということで逢いに行っても、逢ってはくれないあなたであることよ)
帚木の心を知らでそのはらの道にあやなくまどひぬるかな(光源氏)
(近づけば消えてしまう帚木のようなあなたの心を知らないで、私は園原へ行く道に空しく迷い茫然としているかのようです)
数ならぬふせやに生ふる名の憂さにあるにもあらず消ゆる帚木(空蟬)
(しがない貧しい家に生えるものという宿世の情けなさに、そこにあるのかどうかもわからないままに消えてしまう、私はそのような帚木なのです)
見て明らかなとおり、源氏と空蟬の詠歌は、それぞれが「古今六帖」の歌に基づいている。源氏の歌には「帚木」と「そのはら」、空蟬のそれには「帚木」と「ふせや」というように、「古今六帖」の当該歌の歌語「帚木」を共通に引用、さらに「そのはら」と「ふせや」をそれぞれに使用することで、それが明確に分かるのである。このことは、「古今六帖」の当該歌への顧慮を、作者が読者に積極的に求める姿勢を表したものとみなければなるまい。つまり、巻名の「帚木」という言葉に、作者は、「古今六帖」の当該歌の持つイメージを担わせたのである。
このことは、紫式部という人が所属する特殊な世界(彰子後宮)に限られることではなく、平安朝貴族社会の歌人たちの一般的な素養であったかと思われる。むろん同じ世界に所属する誰でもがこういうことに敏感というわけでもなかろうが、少なくとも、『源氏物語』の「第一次の読者たち」のほとんどは、巻名「帚木」の最初の提示の段階で、この歌の存在に気付いたのではあるまいか。
そして、「巻名」の「帚木」が、前巻の「桐壺」同様に、あるなんらかの「予告性」を有しているとするならば、それは、この当該歌が持つイメージの世界の提示と言っていいだろう。そのことを具体的に言うならば、「帚木」巻に展開する恋物語が、「ありとて行けどあはぬ君かな」と光源氏が嘆くようなドラマか、あるいはまた、主人公光源氏を待ち受ける恋物語が、「そのはらやふせや」と詠われるような舞台であることを告げようとするのであろう。つまり、「桐壺」巻を承けた「帚木」巻は、主人公光源氏が、「そのはらやふせや」と詠われるような場所に向かい、さらに、そこでのヒロインに対して「あはぬ君かな」と嘆くという恋物語が用意されるのではないかという示唆でもあった。
しかしながら、「桐壺」巻で華々しくデビューした光源氏が、次の巻ではそういう世界(卑賎階層)に出向き、しかも、「あはぬ君かな」と嘆くといったようなドラマは、当時の物語作品の常識的あり方としては考えられぬことであった。だからこそ、作者は、巻の前半において「雨夜の品定め」を用意し、それに「帚木」世界(受領層)への円滑な導入を図るという役割を担わせたのである。「雨夜の品定め」の重さとは、この物語を最上流の世界だけには終わらせぬという作者の深い思念からくる重さでもあった。「帚木物語」に続いて、同様の世界である「夕顔物語」が展開する所以でもある。
なお、蛇足に近いが、「帚木」巻末で、源氏が小君(空蟬の弟)に手引きさせて空蟬に逢おうとするものの、空蟬は邸内の奥に隠れてかたくなにそれを拒否するのは、むろん、この歌の「ありとて行けど逢はぬ君かな」の物語化である。
「ふせや」は仮の宿り
ところで、「そのはらやふせやにおふる帚木」と詠われる「そのはら」は、信濃国にある「園原」なのだが、「ふせや」については、諸注、粗末な貧しい家、とするのが一般的である。それは間違いではないのだが、少し気になるのは、この「ふせや」に、「地名の伏屋に掛ける」(新潮日本古典集成)、「地名の伏屋の森に、しずが伏屋をかけている」(評釈)とする解釈の存在である。「ふせや」は「伏屋」であって、実質的な歌意では粗末な家ということで問題はないのだが、一方の語義としてある「地名」の「伏屋」には、少し気になる事情が出来するのである。
今日の「園原」は、長野県下伊那郡阿智村にある地域だが、「伏屋」については地名としてそれを確認することができない。しかし、和歌で「ふせやにおふる帚木」という言い方をする以上、それを正直に読み取る限りでは「所の名」とするのは妥当ということになろう。しかし、この「ふせや」(伏屋)は、もとは「布施屋」であったということが『国史大辞典』などの解説からわかるのである。
これによれば、「布施屋」は、地名ではなかった。それは古代の主要な「道」に設置された「臨時の宿泊所」を謂う言葉なのであって、その「布施屋」の一つが、東山道の美濃と信濃の国境に設置された「布施屋」なのであった。この「布施屋」が設置された地域が「園原」という所であり、「ふせや」とは、そこにあった「布施屋」が後世地名として残ったものかと思われる。
『国史大辞典』の「布施屋」についての解説によると、この園原地区のものは、最澄(766~822)が造ったものであるという。とすれば、平安時代の中頃にはまだ実際に「布施屋」として機能していたか、あるいは、廃されたとしても、その存在の記憶は明瞭なものがあったとしなければならない。東山道を通行することが多かった当時の受領層にすれば、この「園原」の「布施屋」の存在は、特に親しみのあるものだったに違いない。
「帚木」巻制作当時、平安朝貴族社会に所属する「受領層」にとって、「園原」の「ふせや」とは、あるいは「布施屋」のイメージが強かったかもわからない。むろん当時の「布施屋」は、貧しく卑しい家屋であったはずだから、そういう方向での解釈は正しいとしても、この言葉に「仮の宿り」というイメージも強くあったとすればどうであろうか。
あらためて言うまでもないことだが、「空蟬物語」の舞台は、中川にある「紀伊守邸」であった。そこへは何らかの理由で伊予介(紀伊守の父)の後妻の空蟬が臨時に訪れていたのであり、また、突然の「方違へ」先として訪れた光源氏も、そこを「仮の宿り」として使用することになったのであった。このことは、はたして偶然の符合で済まされるものであるのかどうか。
ただし、「紀伊守邸」は、「布施屋」のイメージとは相容れない豪奢な邸宅ではあった。これは、空蟬があえて「数ならぬふせやにおふる」と詠うことで、自身があくまでも「受領層」に所属する身の上であることを強調したものと思われる。今はけっして光源氏が所属する世界とは相容れぬ、という覚悟にも似た嘆きが、鮮やかに表出されたと言うべきであろう。
「空蟬物語」の枠組みの一つとして、この古代の「布施屋」のイメージ(仮の宿り)を想定してみるのは、作者である「紫式部」も、そして、この物語の「第一次の読者」である同僚の女房たちも、まさしく「受領層」に所属する人々であったことを思えば、けっして意味のないことではあるまいと思われる。