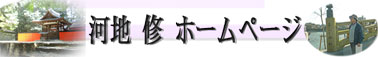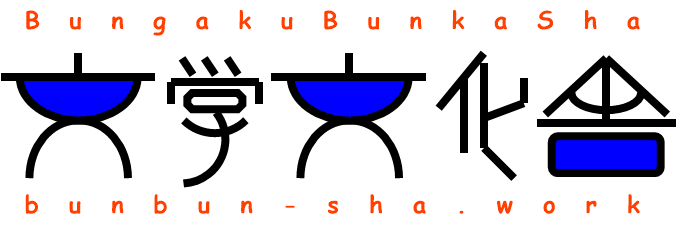-源氏物語講話-
第24回
大い君の死について(十三)
八の宮は薫に娘たちの後見を託したが―
すでに述べたように、八の宮は薫に娘たちの後見を託し、薫も明確にそれに応じた。そのことは、「椎本」巻での八の宮の参籠前の秋、宇治を訪れた時の薫と八の宮との会話、そして贈答からも、はっきりと確認することができる。物語は、その場面に続いて薫の心情を、薫自身の内面に即しつつ次のように語っている。
わが心ながら、なほ人には異なりかし、さばかり御心もてゆるいたまふことの、さしもいそがれぬよ、もて離れて、はたあるまじきこととは、さすがにおぼえず、かやうにてものをも聞こえかはし、をりふしの花紅葉につけて、あはれをもなさけをも通はすに、憎からずものしたまふあたりなれば、宿世(すくせ)異にて、ほかざまにもなりたまはむは、さすがに口惜しかるべう、領じたるここちしけり。
(自分の心ながら、やはり普通の人とは違うことだ。あれほど八の宮様ご自身がお許しなさることを、それほどにも急ぐ気にもなれないことだ、が、結婚など思いもよらないこととは、さすがに思われず、このようにしてお互いに言葉を交わし、時節時節の花紅葉につけて、感動や情趣を通じ合うのに、なかなか素敵だと思われる姫君たちでいらっしゃるので、自分との縁がなくて、他の男と結婚なさるのは、やはり残念に思われるに違いなく、姫君たちはもう自分のものという気がするのであった。)
ここで薫が思う八の宮の「さばかり御心もてゆるいたまふこと」(あれほど八の宮様ご自身がお許しなさること)とは、具体的にはどのようなことなのか―。言い換えれば、薫は、八の宮が自分に対して何をお許しになったと思っているのか、ということであるが、「さしもいそがれぬよ」とか、「ほかざまにもなりたまはむは、さすがに口惜しかるべう、」という薫の気持から推測するに、それは、あきらかに「結婚」のことと考えるほかはあるまい。つまり、薫は、八の宮が姫君との結婚を許したのだ、と確信していることになる。その思いが、「領じたるここちしけり」―姫君たちは自分のものだとする、見方を変えれば不遜とも言えるような自信を得たということになろう。
しかし、八の宮は、姫君たちと薫との婚姻を、はたして現実的にどこまで考えていたのであろうか。八の宮は、たしかに、薫に「後見」を懇願し、薫は、それを確約しへと言うことができる。しかし、ただそれだけのことに終わったのではなかったか―。具体的に言うならば、八の宮は、薫に娘たちの後見を頼みはしたものの、そのかたちは、あるいは、明確に結婚というものではなかったのではないかと思われる。
「婿」と「後見」―八の宮の苦悩は深い
話は少し遡るが、「椎本」巻での冒頭近く、「二月二十日のほど」に、匂宮一行が石山からの帰途、夕霧の別業に立ち寄った場面がある。その時、宇治川を隔てた対岸から聞こえてくる貴公子たちの楽の音に往時を偲ぶ八の宮は、姫君たちのこれからについて、独り言につぶやくようなかたちで、次のように心情を吐露する(おそらく傍で女房が聞いているのであろう)。
かかる山懐にひき籠めてはやまずもがな、とおぼし続けらる、宰相の君の、同じうは近きゆかりにて見まほしげなるを、さしも思ひ寄るまじかめり
(姫君たちを、こんな山に囲まれた田舎に一生暮らさせることはしたくないものだ、とお思い続けられる。宰相の君(薫)が、どうせなら親しく姫君たちの婿にしたいようなお人柄ではあるが、宰相の君は、そのようには考えてみようともしないようだ)
ここで語られる八の宮の心情は、「まめ人」薫への率直な感想に他なるまい。「さしも思ひ寄るまじかめり」には、薫を「婿」とすることは無理だろう、と諦めているように見えるが、しかし、「同じうは近きゆかりにて見まほしげなる」と、同時に、ここには薫を婿とすることへの八の宮の願望があることは言うまでもない。八の宮の気持は、自身の願望(婿としての薫)と現実(まめ人としての薫)との狭間で、微妙に揺れ動いていると言うべきではないか。
この時から少し時間が経ったと思われる頃だが、物語は、唐突に、
宮は、重くつつしみたまふべき年なりけり。
(八の宮は、今年は、重く身をお慎みにならねばならぬ年なのであった。)
と、語るのである。宮が厄年であることを告げるのであるが、これは、言うまでもなく、この年の秋、八の宮が亡くなることへの伏線と考えていい。たしかに、物語構成の上では伏線ではあるが、しかし、同時に、現実の物語世界において、その当事者たる八の宮は、自身に迫り来る「死」というものを意識せざるを得ないことであった。物語は、続いて、近侍する女房の視点で、八の宮の心情を次のように語る。
世に心とどめたまはねば、出で立ちいそぎをのみおぼせば、涼しき道にもおもむきたまひぬべきを、ただこの御ことどもに、いといとほしく、限りなき御心強さなれど、かならず、今はと見捨てたまはむ御心は乱れなむと、見たてまつる人もおしはかりきこゆるを、
(この世に何の執着もお持ちでないので、来世への旅立ちの支度をばかりお考えになるので、極楽往生なさることはきっと間違いのないことであろうが、ただこの姫君たちの御ことどもをご心配になられることは、ほんとうにお気の毒なことで、宮は道心堅固なお方ではあるけれども、かならずや、今は最期と姫君たちを残して逝かれるご臨終の際のお心は乱れることであろうと、お側でお仕えする人もご推察申し上げるのだが、)
八の宮は、いよいよ後世安楽の道のための支度に余念がない。これは、言い換えれば、死出の道を意識するということであろう。それにつけても、後に残る姫君たちのことを思えば、その心は乱れざるを得ないというのである。自ら亡きあとの姫君たちの人生を、いったいどういう手立てで守ることができるのであろうか。それは、やはり、「結婚」ということなのではないか―。物語は、さらに八の宮の心情を次のように語る。
おぼすさまにはあらずとも、なのめに、さても人聞きくちをしかるまじう、見ゆるされぬべき際の人の、思ひ寄りきこゆるあらば、知らず顔にてゆるしてむ
(宮のご理想通りとはいかなくとも、とりあえず人並みで、婿として外聞が悪くはない程度の、世間からもあれならと大目に見てもらえそうな身分の男で、誠心誠意、夫として姫君のお世話をさせていただこう、などという気持ちになってくれる者がいたならば、見て見ぬふりをして婿に迎えよう)
この八の宮の心情を見る限り、やはり姫君たちの将来を安定させることは、「真心に後見きこえむ」という「婿」を迎えることであった。そして、姉妹のうち、一人でも「住みつきたまふよすがあらば」、つまり、どちらかが婿を迎えることができるならば、もう一人の世話も託して、自分としては一応安心できるのだが、と八の宮は思う。しかし、そういう婿候補と言えるような人物はなかなか見つからないのであった。
この苦悩にも似た八の宮の思念こそ、かつて「若菜」巻で提示された朱雀院の女三の宮に対する父としてのそれであった。
我々は、「若菜」巻以降に展開された子を思う親の「心の闇」に臨んだ作者の深い思念に、今再び向き合う機会を得たのである。
この稿続く
一覧へ