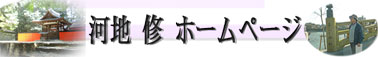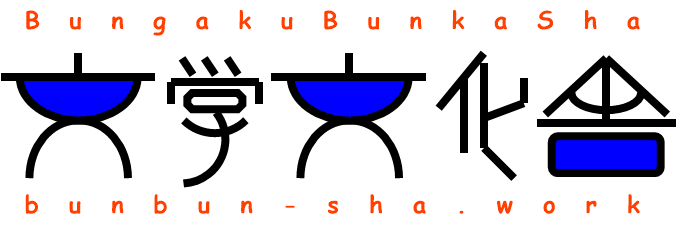-源氏物語講話-
第15回
大い君の死について(四)
「別業」の地の光と影
平安時代、宇治は、王朝貴族が宇治川畔に夏の涼を求める「別業(べつぎょう)」の地でもあった。「別業」とは、今で言えば、別荘ということであって、いつの時代でも同じだが、富の象徴としての存在である。光源氏の須磨退去を受け、一時は立太子の可能性を持った八の宮の没落後の住処として、この別業の宇治の地を選んだ作者の狙いは明確である。一言で言えば、「八番目の宮」の運命に曙光が射し、しかし、その直後に暗転するという劇的な変貌を見せた八の宮の境涯そのものの表徴であった。
光源氏復権の後、八の宮は「あなたざまの御仲らひには、さし放たれたまひにければ」(源氏方のお付き合いからは、遠ざけられておしまいになられたので)という零落の状況となったので、都での生活は、まさしく、困窮の親王家そのものであったろう。北の方との間には二人の姫君を儲けたが、その北の方も亡くなり、八の宮は、姫君を養育しつつも気持ちの上では、「聖になり果てて、今は限り」(隠遁僧のようになり切ってしまって、もうこれまで)と、一切の望みを捨てているという状態なのであった。
そういう八の宮に追い打ちをかけるように、京の邸宅が焼失したのであった。「移ろひ住みたまふべき所のよろしきもなかりければ」(移り住みなさることができるような邸宅で適当なものもなかったので)と物語が語るのは、この時、八の宮には、もはや邸を再建する財力も、また、身を寄せるべき縁故も無かった、ということを物語っている。そういう八の宮ではあったが、「宇治」の地に「よしある山里」を持っていた、というのである。それは、ささやかな規模のものではあったが「別業」なのであった。
言うまでもなく、「別業」とは、本宅とは「別」に成り立つ邸宅であったから、基本的に、本来富豪家が所有するところのものではあった。八の宮がどのような経緯で宇治に別業を所有するに至ったのかは明らかではないが、皇子から「親王」となり、さらに、一時期、弘徽殿の大后方の皇太子・天皇候補としてクローズアップされたことを考えるならば、別業の所有もけっして不自然なことではない。
このように、「宇治」という土地から浮上するイメージは、何と言っても、避暑のための「別業」の地ということであって、それは、「光」が射すように明るいものがあるのではないか。本来そういう富(栄華)の象徴として「別業」というものがある以上、そういう性質の「別業」に、皮肉にも四季を通じて常に住み続けなければならぬという八の宮の宿命は、「光」ゆえにもたらされる「影」そのもののであったと言うことができよう。まさに、富の象徴としての別業が、そのまま負の舞台に暗転したのであった。
ところで、歴史上、宇治の別業として最も代表的なものは、「宇治院」である。左大臣源融(822~895)が設けたもので、今日の平等院にその面影を留めるが、ここが寺院となったのは、藤原頼通が道長から相続した後で、永承7年(1052)のことであった。紫式部が『源氏物語』を執筆していた頃は、道長の「宇治殿」時代であり、むろん、宇治川畔最大の規模を有する別業であった。
この宇治院(宇治殿・後の平等院)は、融の没後、宇多天皇、朱雀天皇と引き継がれ、「宇治十帖」の時代設定となる10世紀後半のころには、宇多の皇孫源重信の所有であった。そういう歴史事情に顧慮したのかもしれないが、「橋姫」巻に続く「椎本」巻では、「六条の院より伝はりて、右の大殿知りたまふ所は、川より遠に」(光源氏から伝領して、右大臣(夕霧)が所有される別邸は、宇治川の向こう側で)と語られるように、宇治院とおぼしき別業が、光源氏から子の夕霧に伝領されたということになっている。そして、「川より遠に」とあるのは、京都側からみて宇治川の向こう岸ということで、そのまま今日の平等院の位置に比定されるのである。この平等院の場所に比定される夕霧の別業は、物語では匂宮が宇治での拠点とする所で、やがて「総角」巻では、対岸の八の宮の山荘との対比において、きわめて重大な役割を担うことになるのだが、今は措こう。
今日の平等院は、もともと別業として営まれたものであることはすでに述べたが、その別業らしい特色として、邸そのものが宇治川に面して建てられていたということが指摘できる。現在は堅固に護岸工事が施されており、さらにその上に道路も建設されているのでイメージしにくいが、別業の当初は、河岸に邸が臨む位置であったと思われる。そして、その邸の建物からは、直接宇治川に突き出る形で、「釣殿」が設置されていたことが明らかになっている。
「釣殿」とは、王朝貴族の寝殿造りに見られる特徴の一つで、東西の対の屋から南に廊を伸ばし、そのまま池の上に設置された小さな建物のことである。たとえば、『源氏物語』の「六条院」の場合は、東南の町(源氏と紫の上が居住)の東の対の屋から廊が南下し、庭園の池に「釣殿」が設けられた。そこでは、名称が示すとおり、釣りを楽しむこともあったであろうが、多くは、夏の暑さを避けるための場所となった。『源氏物語』の「常夏」巻の冒頭では、猛暑の中、この「釣殿」で涼を取る光源氏たちの姿が描かれているのは周知のとおりである。
宇治院の場合は、この「釣殿」が直接宇治川に突き出ていたということになるので、まさに、左大臣源融から道長へと継承された宇治最大の別業にふさわしい贅を尽くしたものと言えよう。
ただし、この釣殿は、宇治川の本流に突き出されたものではなかった。その場所は、宇治川の平等院側の細長い中州(中の島)の手前の部分で、そこでは、中洲の下流側の先端部分から河岸に「堰」が築かれており、流れはほとんど留まっているのである。むろん、もともとはそこに堰を築くことで水位を上げ、南山城地方の農業用水としたものであろうが、王朝貴族たちは、その「堰」の上流側において、嵐山の「大堰川」同様、舟を浮かべて歓楽に興じたのであった。
このように、宇治川は、宇治院側に近い中州を境にして、流れの激しい宇治川本流と穏やかな堰内とに隔たれていることになるのである。むろん、八の宮の「山里」(山荘)は、宇治橋から上流を臨んで左手に位置するのであって、宇治院側の豪奢な世界とは、まさに宇治川の急流が遮ることになるのであった。宇治の物語は、作者の周到な計算によって構築されているのである。

宇治橋上流の「堰」を臨む。手前の橋が架けられている所が、秦氏が築造したとされる人工の「中州」で、今は総称して「中の島」と言われている。堰を流れ落ちた川の水は、中洲の先端で再び宇治川本流と合流する。この写真では見えないが、橋の右手に平等院が位置する。中州の左は宇治川の本流で、流れは激しい。八の宮の山荘は、平等院の対岸、宇治川の本流の側に位置している。