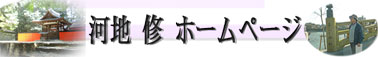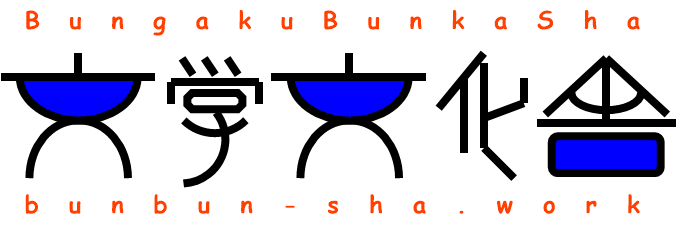-源氏物語講話-
第8回
「六条御息所」考―鎮魂として(三)
「あくがれ出づる魂(たま)」と「生霊(いきすだま)」
六条御息所といえば、何といっても「葵巻」での「生霊」ということになろう。巻前半の車争いの場面における屈辱とその後の御息所の憂悶が、そのまま葵の上を苦しめる物の怪の出現となって展開していくことになるが、左大臣家では、その物の怪を、最初から御息所の生霊として認識していたわけではない。
葵の上を苦しめる物の怪は、「物の怪、生霊(いきすだま)といふもの多く出で来て」とあるように、数多くの死霊、妖怪、生霊であった。その中でも「いみじき験者」(とても効験のある高僧)の加持祈祷にも負けない物の怪がおり、左大臣家の女房たちは、次のようなことを「ささめく」のであった。
この御息所、二条の君などばかりこそは、おしなべてのさまにはおぼしたらざめれば、怨みの心も深からめ
(この御息所と二条院の君などの女君たちだけは、光源氏は並々のご寵愛ぶりではなさそうに見えるので、正室に対する恨みの心も深いものがあろう)
この女房たちのひそやかな「ささめき」には、光源氏の正室である葵の上に取り付く「もの」が、正室に対する「怨みの心」が深いはずの御息所や紫の上であることの可能性を示唆するものがあろう。しかし、あくまでも、それは、彼女たちの見当の一つに過ぎないことであって、結局は、占いの者たちも「聞こえあつることなし」(誰の怨霊かは申し当てることはない)という状態なのであった。
しかし、ここで注意しておきたいのは、「物の怪、生霊(いきすだま)といふもの」が多数現れている中で、女房たちが、漠然とした噂話の段階ではあっても、「この御息所、二条の君など」と、具体的に二人の女性の存在を言葉の端に昇らせているという事実である。このことは、当時、正室以外に「かよひ所」が多くあるような男女の世界においては、時として、恋敵による怨霊めいた話が実際に存在していたということを物語るものであろう。
しかし、そうだとしても、生身の人間に取り付く(攻撃する)「物の怪」が、言わば、正室の恋敵の「生霊」である、というような話は、はたしてどれほど現実味があったものだろうか、とも思われる。
正室とその恋敵(愛人)とが、互いによく思わない(憎み合う)のは、ある意味で自然のことでもあろうから、この場合、葵の上付きの女房たちが、御息所や紫の上といった存在を思い浮かべ、その名前を口の端に昇らせるのはよくあることかもしれない。しかし、実際に、「生霊(いきすだま)」として、物語世界に造型するのは、たとえそれが「物語」のことであったとしても、やや勇気のいることではなかったかとも思われる。というのも、「螢」巻の「物語論」を読んでもわかることだが、紫式部という人は、物語が語る「嘘」について、きわめて敏感に反応する人であったからだ。はたして、当時、この「生霊(いきすだま)」というものは、人々が実際に体験するような話であったのか、なかったのか、というようなことを考えてみたいのである。
実は「生霊(いきすだま)」という言葉の文献上の初出は、この物語のようである。しかし、言葉じたいは『和名抄』にも載っているので、古くからあった言葉かもしれない。語構成から言えば、「生」きている「霊(すだま)」ということで、つまりは、その人の「魂(たま・たましひ)」ということになる。死者の「魂」ではなく、生きている人の「魂」ということであるから、それは、ありていに言えば、「精神」や「心」ということになろう。すなわち、「生霊」とは、人の「魂」がその人から離れて、外へ遊離する現象を指すものと考えていい。それは、肉体の外に出てゆくほどだから、よほど激しく深い心情には違いない。
この時代、「魂」が遊離する、という時に使われる動詞に「あくがる」がある。下二段に活用する動詞で、現代の「憧れる」のもとのかたちである。その正確な語義としては、「本来あるはずの場所から離れる意」(日本国語大辞典)というものであって、「魂」だけに限らないが、しかし、人物がふらふらとそこに出掛けるにしても、対象に心がひかれるからそういうことになるのであるから、やはり、原点は「心」がひかれるということになろう。
この「あくがる」は、『古今集』当時から、すでに和歌の世界で用いられている。次に素性法師の歌(詞書「春の歌とて詠める」)を掲げてみよう(『古今集』「巻二」「春下」)。
いつまでか 野辺に心の あくがれむ 花し散らずは 千代も経ぬべし
(この春の野辺に、私の心はいったいいつまで彷徨うことであろうか、もしも花が散らなかったならば、そのままそこで千年も時が経過することだろう)
春の野に咲く花に、「心」はいつまで「あくがる」ことになるのだろうか、と詠っているのだが、「あくがる」主体が「心」であることに注意したい。また、紀貫之の次の歌も掲げてみたい(『紀貫之集』「恋」)。
思ひ余り 恋しき時は 宿かれて あくがれぬべき 心地こそすれ
(思慕が強くなり過ぎ、あなたが恋しくてならない時は、宿りから離れてふらふら彷徨ってしまいそうな気持がする)
この貫之の歌の「あくがれぬべき」であるが、その主語については、貫之自身の身体とも初句の「思ひ」とも考えられるが、いずれにしても、「思ひ」が「余り」、「恋しき時」は、「あくがれぬべき」―ふらふらと彷徨い出て行ってしまいそうだ、ということで、強く深い物思いによって、「魂」が「あくがる」という発想の歌なのである。
このように、激しい物思いによって、自身から「心=魂」が「あくがる」情態になるのは、当時の人々にとっては、なかば自然に受け入れられていた発想ではないかと思われる。
そして、こうした発想は、紫式部と同時代の人である和泉式部の次の歌に見られることはよく知られていよう。『後拾遺和歌集』から詞書とともに掲げることとする(『後拾遺和歌集』「巻二十」「雑六」)。
男に忘られて侍りける頃、貴布禰にまゐりて、御手洗川に螢の飛び侍りけるを見てよめる
和泉式部
もの思へば 沢の螢も 我が身より あくがれ出づる 魂かとぞ見る
(男に忘れられていましたころに、貴船神社に参詣して、境内の御手洗川に螢が飛びましたのを見て詠んだうた
物思いに悩んでいると、沢辺を飛ぶ螢も、私の身体から抜け出して彷徨う魂かと思われる)
この歌の詞書に登場する「男」とは、藤原保昌だと言われている。和泉式部にとっては二度目の夫で、その婚姻は、和泉式部が中宮彰子のもとに出仕して間もなくのころであった。「忘られて侍りける頃」とは、保昌の訪れがしばらくなかった頃ということで、婚姻関係の破綻を言うのではない。ただ、「男に忘られて」、貴船神社に参詣、そこで「魂」が「あくがれ出づる」ほど「もの思へば」とある以上、和泉式部の心は、この時、夫の夜離れに、激しく苦悩するほどの悲しみに覆われていたに違いない。「男」(夫)を強く愛するものの、しかし当の「男」が自分に振り向いてくれない懊悩を詠っているのである。情況としては、六条御息所と光源氏とのあり方に共通するものがある。
和泉式部は、自身の「あくがれ出づる魂」を「沢の螢」に見立てたが、「葵」巻の御息所の場合もまた、その「魂」が「あくがれ出」た結果の「生霊」であった。実は、御息所自身も、当時「あくがれ出づる魂」というものが存在するというようなことを認識していたのである。
身一つの憂き嘆きよりほかに、人をあしかれなど思ふ心もなけれど、もの思ひにあくがるなる魂は、さもやあらむと、おぼし知らるることもあり。(中略)
あな心憂や。げに身を捨ててやいにけむと、うつし心ならずおぼえたまふをりをりもあれば、
(自分だけのつらい嘆きのほかに、葵の上の身に不幸があれ、などと思う心はないけれど、深く思い悩むと、身体から離れて彷徨うと言われている魂は、そういうこともあろうかと、お思いになられることもある。(中略)
ああ何と情けないことだ。ほんとうに魂が身体から離れて行ってしまったのだろうかと、正気ではなく思われなさることも度々あるので、)
このように、御息所自身、「あくがるる魂(たましひ)」の存在が、当時世間で伝聞されていることを知っており、なおかつ、自身の夢で、葵の上らしい女君のところへ行って、「うちかなぐる」(荒々しく打つ)姿が見えるというのであった。それは、自身の「うつつにも似ず」―自分の本心とは違うものではあったが、しかし、そういうことが噂される「宿世の憂き」により、もう源氏のことは忘れようと思うものの、その思いもまた激しい物思いなのだと、悲しく苦悩するしかないのであった。
このように、六条御息所自身が「あくがるる魂」の存在に思いを致し、自身も、そうなのかもしれないと苦悩する物語世界とは、いつの時代でも存在する「死霊・怨霊」の概念に、当時ごく自然に信じられていた俗信―深く激しい苦悩がやがて「あくがれ出づる魂」になる―という認識を結び付けて造型された「生霊(いきすだま)」のドラマなのであった。けっしておどろおどろしい「生霊」というようなものではなかった。
六条御息所の「生霊」の話は、その根底に、当時の女たちの情念の世界に実在した「あくがれ出づる魂」という深い哀しみの存在があることを忘れてはなるまい。