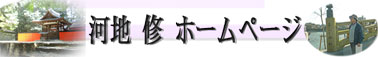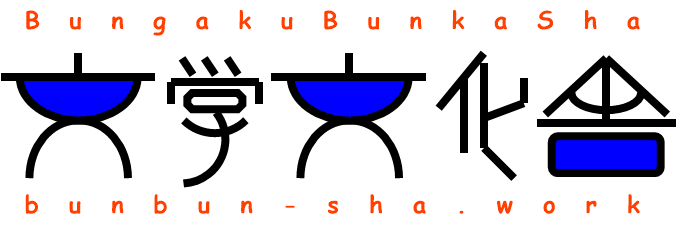-源氏物語講話-
第6回
「六条御息所」考―鎮魂として(一)
ヒロインとしての六条御息所
六条御息所は、間違いなく『源氏物語』中のヒロインである。もちろん少し厳密に言うなら、ヒロインの一人、と言うべきではあろう。
彼女は『源氏物語』の端緒部分に近い「夕顔巻」にいちはやく登場しているし、「葵巻」では、おぞましい「生霊」として光源氏の正妻「葵の上」を死に追い遣るとはいえ、思うように愛されない女の心情が縷々吐露される点、あるいは、当の「葵の上」にまさるヒロインと言えるかも知れない。
また、朱雀帝の即位により、娘が「斎宮」に卜定され伊勢に下る際には、源氏を思い切るため娘との同道を決意するが、逆にそのことに憐憫とする源氏の訪問を受け、そこで描かれる別離に際しての愁嘆の場面は、古来「野の宮の別れ」として名高い(賢木巻)。
さらに、彼女は、死後の怨霊―いわゆる「死霊」としても登場する(若菜下巻)。そこでは、「死霊」とはいえ、自身の、生涯にわたる源氏への満たされぬ思いのたけを痛切に訴え、その愛執にもがき苦しむ女の姿は、哀切極まりないものがある。
このように、六条御息所は、「光源氏物語」のほぼ全編に渡って登場するヒロインとして、その存在は異彩を放っている。そして、この異彩の放ちかたは、なんと言っても、物語のヒロインの中で、唯一「怨霊」(生霊・死霊)としても登場することで、その印象は強烈なものがあると言えるのである。
しかしながら、エンターテイメント(娯楽)の要素が強い「物語」において、ヒロインが「怨霊」そのものになるということは、他の物語でも、ほとんど例がない(道成寺縁起の清姫ぐらいか)。むしろ、物語のヒロインは、怨霊に苦しめられる側というのが一般的なパターンであって、物語中の他のヒロインを苦しめ、さらには死に至らしめるというようなパターンは、すでにその時点において、物語のヒロインとしての資格を失うと言ってもいいかもしれない。
しかし『源氏物語』の場合、六条御息所は、そういうおぞましい「怨霊」として、しかも「生霊」―「死霊」へと変化(へんげ)の形を示しつつも、最後まで物語のヒロインとしてあり続けた、と言わなければならないだろう。
六条御息所の登場―「朝顔」のイメージ(「夕顔」との対比)
六条御息所は、「夕顔」巻で初めて登場する。しかし、彼女は、そこではけっしてメインの存在としては語られない。この巻のヒロインは、あくまでも夕顔であり、それは「巻名」の「夕顔」からも明らかである。この巻での六条御息所について、たとえば、玉上琢弥博士は『源氏物語評釈』のなかで、夕顔という女の身分ゆえの、ある種「イメージの悪さ」の回復と修整のために、この六条御息所のような高貴性溢れる世界が必要となった、と述べておられるが、だとすれば、「夕顔という女」の表徴として、巻頭に「夕顔」の花の描写が詳細に描かれ、また、その一方で、巻の中盤、六条御息所邸の庭の「朝顔」の花が印象的に描かれるのは、まさに、この巻において、「夕顔」(俗)と「朝顔」(雅)との強烈な対比が意識されてのことと認めることができよう。
今でこそ「夕顔」という言葉は、雅やかな語性を有すると言っていいが、この物語の制作当時、この言葉の概念は、今言うところの「干瓢(カンピョー・ユウガオ)」に過ぎなかった。清少納言は『枕草子』「花は」のくだりで、次のように言っている。
夕顔は、花のかたちも朝顔に似て、言い続けたるにいとをかしかりぬべき花の姿に、実のありさまこそいとくちをしかりけれ。などてさは生ひいでけむ。ぬかづきといふもののやうにだにあれかし。されど、夕顔といふ名ばかりは、をかし。
(夕顔は、花の形も朝顔に似ていて、朝顔夕顔と言い続けるととても素敵なはずの花の姿なのに、その実のかっこうがなんとも残念だ。せめて、ほおずきというもののようであってほしいものだ。しかし、なんと言っても、夕顔という名だけは、素敵だ)
ここで示される清少納言の認識がおもしろい。「夕顔」は、花とその名は、「朝顔」に通じるものがあっていいが、しかし、実のかたちだけはいただけないというのである。
実はともかく、「夕顔」の花は「朝顔」のそれに似ていると言い、さらに、「朝顔」「夕顔」と言い続けると雅趣(をかし)がある(「朝霧、夕霧」「朝露、夕露」などからの連想があろう)と言っているのは、「朝顔」との対照の妙を指摘しているものと思われる。しかし、何と言っても、「夕顔」の欠点は、「実のありさま」だと言うのである。この「実のありさま」こそ「干瓢」の姿であり、このような俗性あふれたイメージが、当時の「夕顔」のそれであった。たとえば、「夕顔」は、『源氏物語』以前は、いわゆる歌語としては、まったく用いられていないという事実が、何よりもそのことを物語っている。
一方、「朝顔」とは、古く『萬葉』の時代から歌われてきた伝統の歌語(『古今集』では五首歌われている)であり、「夕顔」巻において、この言葉の放つ雅性が鮮やかに付与されたヒロインこそが、六条御息所その人であったと言うことができるのである。
従って、この俗性そのものの「夕顔」という語彙を巻名に採用した紫式部はエライということにもなるのだが、ただ、『枕草子』の当該の箇所で、清少納言は、次のようにも言っている。
されど、夕顔といふ名ばかりは、をかし
(しかし、なんと言っても、夕顔という名だけは、素敵だ)
「夕顔」は、その名だけは素敵だというのであるから、このくだりは、紫式部が「夕顔」を巻名に採用したのと同じセンスと言っていいのではないか。紫式部が、その当時、実際に『清少納言枕草子』を読んだかどうかはわからないが、ともかく、同時期、ほぼ同一の環境において厳しく対峙する姿勢で生きていた二人が、「夕顔」という語彙については、その特性を同じく積極的に評価していたことはおもしろい。