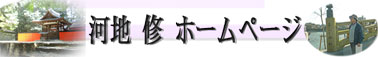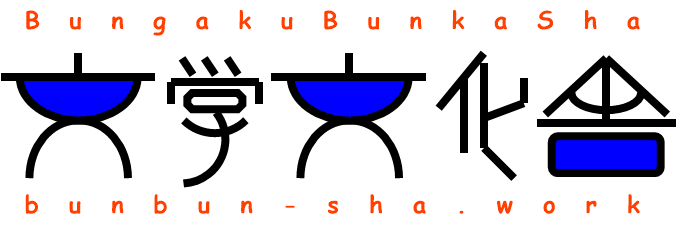-源氏物語講話-
第3回
「巻」の独立性と「巻物仕立て」―「巻子本」から「帖」「冊子本」へ
「ゲンジ、ゴジュウヨマキ」
『源氏物語』の「五十四巻」は、紫式部と呼ばれる作家が書いた。彼女は、どのように書き、そして、それはどのようなかたちでこの世に現れたのか、というようなことを、なるべくリアルに考えてみたい。
私の考える手掛かりは、今に残っている“言葉”しかない。たとえば、「源氏五十四巻(ゲンジ、ゴジュウヨマキ)」と言う。この表現であるが、なぜ「巻」なのか、ということがある。「源氏五十四巻」とは確かに言うのだが、「五十四帖」と言う場合もある。しかし、とにかく、このように「巻」という名称が残っていることから、もともと『源氏物語』が「巻物仕立て」であったことを想像することは可能なのではないか。現物が実際に残っているわけではないので、確証はないのだが、ただ「書物」の製本の歴史は、明らかに「巻子本」から「冊子本」への過程を経ていくので、「巻」という言葉が残っている以上、『源氏物語』の最初の形態が「巻物仕立て」であったことは充分に想像できる。
そこで、『源氏物語』が、もともと「巻物仕立て」、いわゆる「巻子本」であったと仮定するならば、この物語の有する基本的性格とでも言うべきものが、ある程度理解できるようにも思われる。
この物語が制作された11世紀初頭(1008年頃)は、そろそろ「冊子本」が出現していた。その最も著名なケースが『枕草子』ということになろう。当時「冊子本」は珍しかったようで、藤原伊周から中宮定子に献上されたものに、清少納言があの内容(枕草子)を書いたと、いわゆる「跋文」には記されている。
ところで、「巻物」に書くのと「冊子」に書くのとでは、その自由度は圧倒的に「巻物」にあったであろう。「巻物」の場合、基本的に「料紙」を継ぎ足してゆけばよかったわけだし、書き物が完成した時点で巻き上げてしまえばよかったからである。ところが、最初から「冊子」になっていれば、すでにその分量は決められているので、内容面での自由さはあまりなかった。また、後から「冊子」に製本したとしても、綴じ製本を可能とする一冊の厚さという制約があるわけで、やはり、分量の面からいっても、限度はあるにせよ、圧倒的に巻物の方が有利であった。
つまり、分量面でより柔軟性があるのが「巻物仕立て」であり、それは、作品の中身の自由度をも、ある程度保証するものであったろう。
その点、『源氏物語』は、その制作の段階において、あらかじめ長短様々なものになることが許されていた、と言うことができるのである。このことが、「巻」によっては、回想する人物(語り手)が異なるという『源氏物語』の構想上の特性に、うまく合ったということにもなる。また、回想の内容(話の内容)によっては、長くなる場合も短くなる場合もあるだろう。紫式部は、そういう当初の「巻物仕立て」の特性をうまく利用して、この物語の「仕掛け」を用意したと言うことができる。
「巻」を繋ぐ
このように、巻物の特色として「巻」毎の“独立性”が高いことが挙げられよう。独立性が高いということは、作品全体の有機的繋がりに脆弱性があるということになるのだが、この作品の場合、最初に制作された“巻”は、あるいは、“長編”的意識は、さほどは強くはなかったのではないかと思われる。
私の恩師である故石田穣二博士は、『源氏物語』の起筆を「若紫」と考えておられた。その次にいわゆる「帚木三帖」が書かれ、いつの時点かはわからないが、やがて本格長編物語の構想のもとで、あらためて「桐壺」が用意された、とおっしゃっていた。私は、この考え方は、きわめて合理的なものではないかと思っている(実際の巻の成立順ということではない)。
今、仮に、最初「若紫巻」が制作されたと考えるならば、それは、『伊勢物語』「初段」への深い“読み”―「解釈」と言ってもいいが―に基づく物語世界の再生作業であった。作者は、そういう“テーマ性”を有する独立性の高い物語(若紫)を制作しながらも、見て分かるように、それは、後の長編的構想にも耐えられるように、“布石”を置くことを忘れなかったと言うことができる。その長編への対処と考えていい“布石”こそ、紫式部の、新しい“物語”(『源氏物語』である)制作への強い自負と自信の表れだったのではないかと思われる。
が、ともかく、『源氏物語』という作品は、当初から一巻毎独立性の高いものとして制作されたと思われる。今仮に、「若紫」の後、「帚木三帖」が制作されたと仮定するならば、それは、主人公光源氏の相手役であるヒロインの拡大と展開にあった。別の言い方をするならば、光源氏の青春のアバンチュール―それはけっして明るみに出てはならなかった隠された恋のエピソード―を彩るヒロイン、「空蝉」「夕顔」との恋愛譚の紹介であったというわけである。
これらの恋愛譚は、ほぼ同一の時期のものであり、また同一のテーマ性を有するものであった。その意味において、それらは繋がれているものでなければならなかった。その“繋がり”を示すという意味において、「帚木三帖」という言い方での「帖」という語彙は、正しい用い方と言えるであろう。
さらに想像を重ねてみるならば、この「三帖」は、比較的早い時期において、「帖仕立て」になっていたのではないかと思われもするが、むろん、今となっては確かめようもない。
ところで、「源氏五十四巻」という言い方とともに、「源氏五十四帖」、あるいは、「宇治十帖」「帚木三帖」というような言い方がある。この場合の「帖」とは、もともと分量の単位であったが、やがて「折り本」のことを言うようにもなった。すなわち、「巻物」のように中の料紙が繋がってはいるが、それを折り畳むことによって、「巻物仕立て」に「冊子本」の“機能”を取り込んだものと言えるだろう。
従って、当初「巻物」として誕生したこの物語は、やがて「帖(折り本)」としても制作、あるいは書写されていったのではないかと思われる。そして、製本の歴史は、その後、一気に「綴じ本(冊子本)」の時代へと展開していったことにあわせて、現存写本のほとんどは、冊子本となったのである。
ところで、最初の話題に戻るが、この物語が「巻子本」(巻物仕立て)として出発したということは、大きな意味がある。なぜなら、「巻物」の場合、その総数に「序数」が付されていなければ、全体が一度に提供された場合、どの巻から読んでいいのか分からなくなるのである。どうも、『源氏物語』全体を通して、当初「序数」が付されていた痕跡は見いだせない。ということは、当初は、制作されたもの(巻物である)から順次、彰子に献上されていったものと思われる。つまり、彰子にすれば、献上されたものを“順番”に楽しんでいけばよかったのであるから、巻物でもいっこうに構わなかったのであろう。