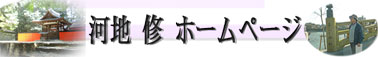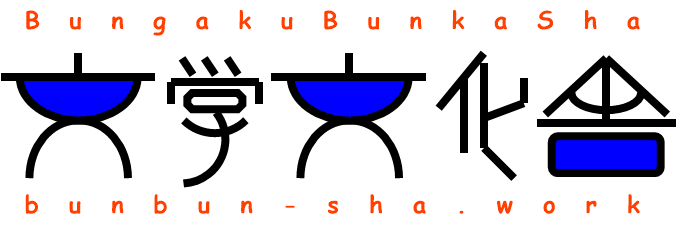講義余話
道真の悲劇(3)
寵愛と嫉妬
人の世の「負」の淵源として、嫉妬ほど手に負えないものはない。よく、女の嫉妬は可愛いが、男の嫉妬はどうにもならない、というようなことを聞く。女の嫉妬が可愛いかどうかはともかくとして、男のそれは、確かに始末に困る。私の人生においても、この手の人間は職場にいたし、実際、始末に困るほどの被害にも遭っている。不愉快であること言うを俟たないが、その不愉快さとは、人間としての根源の愚かさを見る、そういう次元の不愉快さである。
さて、道真のことである。道真は、天皇家傍系から即位した宇多天皇に重用された。宇多天皇にすれば、門閥(藤原北家)出身ではない道真という人材に、律令に基づく理想的な親政の実現を夢見たのであろう。
すでに述べたことだが、道真は讃岐の国司に任ぜられている。善政を敷いたと言われているので、その国の民に対して、今の感覚で言うところの減税でも行ったようにも思われるが、おそらく、それまでの国司とは異なる方針を示したのであろう。当時の国司は、皆が皆すべてというわけではないにせよ、その多くは、朝廷に送る税よりも多く徴収し、残ったものは自分の懐に入れた。
『源氏物語』「帚木」巻で、光源氏が、夏の夜、正妻である葵の上のもとから突然押し掛けることになる紀伊守邸は、光源氏の部下筋にあたる人物の邸宅であった。紀伊守であるから、今の和歌山県知事のようなものである。その紀伊守邸は、京の夏の暑さを凌ぐために、近くの川から水を引いていたというから、相当に贅を凝らしたものであった。
また、その父は「伊予介」であった。この父も国司である。「伊予」は今の愛媛県である。「介」とは、厳密にいえば次官であったが、伊予国の場合、「守」が親王の遙任(実際には赴任しない)であったから、「介」は実質的なトップであった。この父は、空蝉の父が死んだ後、後妻として空蝉を娶り、さらにその弟の小君を引き取った。裕福だったのである。しかし、源氏の部下筋ということで、このことが、源氏をして、「空蝉」への強圧的な逢瀬を取らしめる要因となったのである。
このように、光源氏と国守との間で絶対的上下関係が生じるのは、その任命に当たっての権限を、源氏方の勢力(左大臣)が握っていたからにほかならない。つまり、左大臣の勢力(源氏方)が、国司任命ポストの一定数を握っているということであった。受領層(中流貴族)は、生きていく上で、当然任命権を持つ権門への追従が必要であった。そして、その結果として、ポストの配分に預かることになれば、彼らはその恩義に、当然報いねばならないし、そのためには、中央政府に納める税額以上のものを徴収せねばならなかったのである。
明石巻に登場する明石入道も、播磨国の国守であった。そこは現在の兵庫県であり、ゆたかな土地であった。国守時代のことは詳しくは語られないが、この間、莫大な財をなしたかに見える。娘の明石君は、そういう財が背景になければ、光源氏の妻の一人に数えられることはなかった。
従って、国司の中には、強欲なものも出現し、必然的に圧政を強いることにもなったし、その一方で、それに領民が反発する事件も起こった(尾張国司苛政上訴事件、974年)。そういう国司のやり方が、多寡は別として、当時常態化していたとすれば、道真の地方行政は、讃岐国の領民の立場からは新鮮だったに違いない。
そういった道真の清廉とも言える地方行政への姿勢は、律令に基づく政治として評価された。その評価が、前述のとおり、学問の家の菅原氏出身としては異例の出世を遂げさせたと言えるのである。そして、ついには、右大臣にまで昇った。
確かに異例の出世ではあった。家が大学寮文章博士の家系であって、優秀な道真が博士になる―ここにも嫉妬の要因がないわけではないが、同僚たちにとっては、その種の感情は何とか抑えられたように思われる。ただ、宇多天皇の重用とそれに伴う政治的昇進は、学問の世界から大きく踏み出し過ぎたのではなかったか。同僚たちは嫉妬した。それは、始末に困る醜い嫉妬であったに違いない。
それでも、宇多天皇は、道真を重用し続けた。藤原基経も、地方行政における道真の姿勢は評価したようである。だからというわけではあるまいが、宇多天皇は、あきらかに道真に肩入れし過ぎたのではないかと思われる。
宇多は、博士である菅原道真という人間に、従来の門閥政治に代わるところの律令政治の復活を賭けたものと思われる。が、あるいは、それだけではなく、そこには、宇多天皇ならでの、きわめて人間臭い、ある特殊な感情が働いていたのかもしれない。それは、宇多の父光孝天皇のことである。
前帝である父親の光孝天皇は、元慶八年(884)、陽成天皇の突然の譲位により即位した。そのことは、時の最高権力者であった藤原北家基経の意思によるものであったが、次ぎに、立太子のことがあった。ふつう天皇の即位は、それと同時に、皇太子に誰を立てるかというきわめて重大かつ深刻な決断を迫られることになるからである。この立太子のことを過つと、当該の皇太子自身が、そのまま生命の危機にさらされることは、それまでの歴史を学べば、誰でも容易にわかることであった。
光孝は、当然のことながら、自分を天皇にした基経に遠慮した。光孝は、自身の実子が皇位継承に関わることを極端に嫌い、即位後所生の子をすべて臣下に下したのであった。すなわち、天皇の持つ皇太子の指名権を、みずから放棄したのであった。それは、後に即位する宇多天皇も例外ではなく、彼は早くから臣籍降下していたのである。光孝は、徹底して、藤原北家に従順であることを示そうとしたと見える。それは、傍目から見て、滑稽なほどの懼れようであったが、それが子どもたちの身を守る唯一の手段と思っていたのであろう。そういう今上帝である父親の姿を見て、子が何も思わないはずはなく、この時、後の宇多天皇の藤原北家(藤原基経)への思いは、複雑なものが生じたに違いない。たとえば、即位直後に基経との間に起こった確執(阿衡の紛議)は、その発端としては、同門の文章博士間の嫉妬の感情に端を発しているが、宇多にとっては、消え難い無念の傷として残った。
宇多の親政へのこだわりは、裏返せば、藤原北家への私的思念としての抵抗でもあった。そして、大義としての律令に基づく親政実現のキーマンこそ菅原道真であったということになる。
こういう言い方もおかしいが、一方で、宇多は、心底道真が好きだったのではないか。宇多は、道真の娘の衍子を、自身の后(女御)として迎えている。寛平八年(896)のことであった。この時、道真は従三位権中納言であったから、その娘の女御としての入内は、厚遇過ぎるものがあった。ここにも、同僚たちの「嫉妬」の感情が増幅したことであろう。帝から特別に信任され寵愛されるという個人の問題として、これらのことは、大学寮の同僚たちだけではなく、貴族社会全体が嫉妬したのではなかったかと思われる。
道真は天皇の信任が厚かったから、その娘が「女御」として迎えられて何が悪いのか、と言う人がいるとすれば、それは、菅原氏の出自のこと(土師氏)を忘れていると言わなければならない。気の毒だが、道真の出自の低さは、彼が栄達すればするほど、当時の貴族社会においては、その原点に遡りそれを再認識しようとする悪意が露骨に働いたことであろう。そのような醜悪な作用は、当時の王朝貴族社会に限ったことではなく、今日の日本社会においても、ごく普通に見られることではあるが―。
ともかく、衍子の入内は、同僚たちを始めとして当時の貴族社会全体の嫉妬を買った。しかし、次のケースは、ただの嫉妬に終わることなく、道真にとっては多分に致命的なことになったのではなかったか。
寧子の場合
道真は、衍子入内の翌年、寛平九年(897)、その下の妹の寧子を、宇多天皇の子である斉世親王(ときよしんのう)の后とした。この年は、宇多が譲位し、醍醐が即位した年であった。同時に、道真は権大納言に昇進したので、道真は、この時政権の中枢を占めつつあった。おそらく、その婚姻は斉世親王の元服の前後と思われるから、寧子は「添臥(そいぶし)」であったろう。「添臥」とは、ほとんど正妻というべきものであり、もしも、この寧子が子を産んだなら、道真は、いわゆる外戚(外祖父)となるのである。これは、むろん、宇多の強い要請によるものだったと思われるが、この場合、道真は慎重であるべきだった。何故なら、斉世親王は、いわゆる「親王宣下(しんのうせんげ)」の手続きを経た(皇位継承権を持つ)醍醐天皇の異腹の弟であったからだ。
今上帝の弟で、皇位継承権を持つ親王の立場は微妙なものがある。このことは、きわめて人間的機微に関わることなのである。すなわち、相続の問題である。天皇に限ったことではなく、常識的に考えれば、人は、自身の後継相続の希望は、「弟」ではなく「子」であること、自明のことであろう。わかりやすく言えば、醍醐天皇の場合には、心情的に、自身の後継は、自身の子でなければならず、そういう意味では、親王の資格を持つ「弟」(特に異母弟)の存在には敏感過ぎるほどのものがあったと言っていい。
現在と違って、古代日本の皇位継承のあり方は、特に決まりがあるわけではなかった。天皇は「日の御子」であり、皇太子は「日嗣ぎの御子」と呼ばれた。要は、世襲であればよかったわけで、血の繋がりというものが絶対視されたのである。
血の繋がりという観点からすれば、天皇の後継は、むろん、その「子どもたち」であればよかった。古代天皇の婚姻関係は、その后たちのそれぞれの出身豪族との関係でもあったから、その後継としては、次の兄弟たち、というような考え方も生まれたのである。すなわち、弟を「皇太弟」とする皇位継承である。実は、平安時代に入ってからも、この「皇太弟」が「皇太子」に優先するという事例は多い。例えば、桓武天皇の場合、当初は、その後継は、皇太弟の早良親王であったことはよく知られている。さらに、その早良親王を廃した後に皇太子となった平城天皇も、即位とともに、同母弟の神野親王(後の嵯峨天皇)を皇太弟としている。
話を醍醐天皇に戻すが、醍醐の場合、父の宇多がもともと臣籍であったから、当然、臣籍の身分で生まれた(元慶九、885年)。親王宣下は、寛平元年(889)に行われ、立太子は、寛平五年(893)であった。即位は、元服した年の寛平九年(897)のことであったから、この年は、道真が寧子を斉世親王の后とした年ということになる。さらに、当たり前のことだが、醍醐が即位したということは、宇多が譲位し、宇多上皇となったということであった。
この年の醍醐には、まだ子がいなかったわけであり、次の皇位継承の問題(皇太子)は微妙な時期であった。すなわち、その時の異母弟であった斉世親王には、リアルな問題として、皇位継承として立太子の可能性があったのである。あるいは、宇多上皇は、近い将来に実行されるであろう北家出身の后の入内の前に、醍醐後の路線のことを考えたとも思われる。ともかく、宇多の場合、醍醐の後の皇太弟として、斉世親王を考えなかったとする見方の方が難しいのではないか。そして、その斉世親王の後見が菅原道真ということであったから、寛平九年(897)当時、藤原氏の氏の長者となっていた大納言藤原時平もまた、けっして心穏やかではなかったであろう。
この時、藤原時平は二十七歳であった。時平は、藤原基経の長男である。当然のことながら、基経亡き後の北家の政権維持とその発展に努める責務があった。しかし、後に醍醐の中宮となる藤原穏子(時平の妹)は、醍醐天皇元服のこの年(寛平九年・897)まだ十二歳であり、入内には少し早すぎた。
穏子の入内は、その四年後の九〇一年であったから、仮に皇太子を立てるとすれば、宇多上皇の親王である斉世親王を皇太弟として立てることは十分に蓋然性のあることだったのである。
そういった状況の下、昌泰四(九〇一)年一月、藤原時平は、道真が醍醐天皇を廃し、娘婿の斉世親王を即位させようとしていると、醍醐天皇に進言した。醍醐はこれを受け容れ、道真を太宰員外帥(権帥)として左遷させるに至るのである。
後世、これを、「昌泰の変」と言うが、時平の讒言ではあったろう。しかし、当時の歴史的状況を読めば、宇多上皇が、醍醐に対して、皇太弟に斉世親王を立てる内意を示していたと言えなくもなく、もしも、斉世親王が皇太弟となり、そのまま即位すれば、皇統が、醍醐から斉世親王に変わる可能性が出てくることにもなるのである。それは同時に、外戚(後見)が、菅原道真になることでもあった。
しかし、この将来像は、時平には、とうてい受け入れ難いことであったに違いない。基経の長男であり北家の氏の長者の時平にとっては、醍醐の後継は、あくまでも藤原北家を外戚とする親王でなければならなかった。すなわち、時平の妹の穏子の入内は決まっていたから、その穏子所生の親王こそ皇太子であるべきだった。ここに、醍醐天皇と時平の思惑は、みごとに一致したのであった。
菅原道真は、昌泰四年(901)まで、よく持ったと思う。それは、学者の理知と清廉さと、そして宇多天皇の強力な後ろ盾があったからである。理屈から言えば、社会を立て直すには、租税の徴収システムの公平にして厳格な再構築が必要であった。これは改革である。しかし、それぞれの地方で租税の徴収に当たる国司にとっては、このような改革は迷惑な話であったろう。早い話、厳密に国庫に納めるだけの租税を徴収していたのでは、有力貴族の実力者たちへ投資した原資は取り戻すことができないのである。
律令(法)という原理原則だけでは、この国はけっして動かないということを、彼らはよく知っていた。道真の受難は、当時の貴族社会全体の道真個人に対する強い嫉妬の感情と、律令という法の枠だけでは物事は動かないという反撥とが、複雑にして微妙に絡みあった結果だと言わねばならない。
ともかく、道真は、太宰府に沈淪した。子どもたちも追放された。激しい憤怒の情は、そのまま彼をして憤死させるに至った。この「才」(ざえ)の人に、仮に、この国の政治をもう少し担当させていればどうなったか。あるいは、もう少し、王朝貴族社会は持ったかもしれないが、そうなったとしたら、道長の栄華も現出しなかったかも知れない。それはそれで、なんとなく寂しいことのようにも思える。なぜなら、道真が目指した厳格な律令政治とは、藤原北家のみが富を独占できる栄華を生まなかったであろうし、ということは、必然的に彰子後宮もあのようなかたちではなかった。とすれば、紫式部も『源氏物語』もこの世には生まれなかったかもしれないということで、後世の私どもとすれば、なんとなく複雑な思いを持つことになるのである。