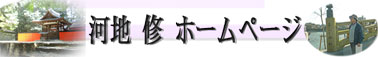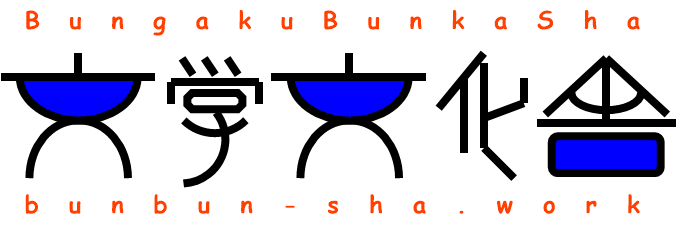講義余話
『古今和歌集』のメッセージ(六)
平城天皇後の和歌事情―唐風謳歌時代
「唐風謳歌時代」とは、いわゆる「国風暗黒時代」の裏返しの謂い方である。「国風暗黒時代」という学術用語は、むろん、専門家が世に送り出したものであるが、語構成は、「国風」が「暗黒」ということだから、なんとなく「国風」は何もないというイメージが強い。だが、「国風」とは「くにぶり」、すなわち「国の文化」ということだから、それが「何もない」ということなどあり得ない。だから、この「国風暗黒時代」という言い方には、解説がいるのであるが、しかし、この語のイメージは強烈であった。私は、学生にこの言葉を説明する際には、「唐風謳歌時代」の裏返しの言い方に過ぎないといつも言うようにして来たが、言葉やそこから導かれるイメージは、一人歩きをするもので、はたして誤解を与えずに済んだかどうか、自信がない。
たしかに、嵯峨天皇の時代から次代の淳和天皇の時代は、日本文学史としては漢詩文芸が最も隆盛した時代であった。「勅撰三集」と呼ばれる勅撰の漢詩集(『凌雲集』・『文華秀麗集』・『経国集』)が相次いで編まれたし、嵯峨天皇を筆頭に、多くの廷臣たちが、漢詩を創作した。平安時代の幕開けとなる9世紀初頭からは、日本文化史においても、まさに「唐風謳歌」と称するにふさわしい文化(弘仁・貞観文化)が華開いた。
他方、「国風暗黒」という言い方であるが、たしかに、この9世紀初頭から後半にかけて、文学史年表を眺めてもわかるが、国文学作品(日本語で書かれた作品)は「皆無」と言っていい。しかし、この「皆無」という捉え方が誤りであることを伝えるのが『古今和歌集』なのである。
実は、『古今和歌集』の作品名称である「古今」の「古」こそ、9世紀、もしくは9世紀前半期を中心とする時代を指しているのである。つまり、『古今和歌集』には、『萬葉集』から『古今和歌集』に至るまでの「和歌」が、確実に収載されているということになる。『古今和歌集』は、平城天皇後の和歌事情を強く意識していると言っていい。
『古今和歌集』「序」が言う九世紀の和歌事情―「好色之家」「乞食之客」
周知のとおり、『古今和歌集』の成立は、10世紀初頭の905年だが、この歌集の「序」である「仮名序」には、次のような記述があることに注目したい。
今の世の中、色につき、人の心花になりにけるより、あだなる歌、はかなき言のみ出でくれば、色好みの家に埋もれ木の人知れぬ事となりて、まめなる所には、花すすき穂に出だすべき事にもあらずなりにたり。
(新しい時代となって、世の中が華美を求めるようになり、人の心も浮薄になってしまったから、和歌も実のない、表面的なものばかりになって、色好みの間に埋もれて、一般には人に知られぬものとなって、公の席などには、ほとんど出すことのできないものとなってしまった)
ここで言う「今の世の中」とは、「新しい時代」ということで、平安京遷都後の時代を漠然と指している。中古語の「今」は、時間の概念の範囲が広く、たとえば、この「今の世の中」を『古今和歌集』が成立した醍醐天皇の時代、などと狭く限定して捉えると、醍醐天皇の時代に和歌が「まめなる所」(公的世界)に出せなくなったということになって、それは、あきらかに誤った判断になってしまうのである。
「今の世の中」とは、具体的に言うならば、9世紀に入ってから、という理解でよかろうと思う。つまり、『古今和歌集』は、「仮名序」において、平城天皇後の和歌については、ほとんど公の席(まめなる所)には出せないものとなっていたと言っているのである。したがって、平城天皇によって『萬葉集』の封印が解かれたものの(806年)、薬子の変(810年)直後の嵯峨天皇の時代から『古今和歌集』誕生(905年)までの間、和歌は公的空間から姿を消したということになるのである。このように考えるならば、薬子の変が日本文学文化史に与えた影響は、けっして小さなものではなかったと言えるのであって、この事件以降、「やまとうた」には、公の場―天皇のもとには出せないという苦難の歴史が刻まれたのであった。
それでは、この9世紀、実際には和歌はどうであったのか―。それを「仮名序」は、簡潔に「色好みの家に埋もれ木の人知れぬ事」となった、と言うのである。「色好みの家」とは、「恋の世界」と言い換えてよく、むろん、それは私的な世界であって、「まめなる所」とは対極に位置するものであることは言うまでもない。
そして、このくだりについて、「仮名序」の草稿的存在とされる「真名序」は、さらに注目すべき見解を提示している。以下、本来は漢文であるが、書き下し文で掲げてみよう。
彼の、時は澆漓に変じ、人は奢淫を貴ぶに及びて、浮詞雲のごとく興り、艶流泉のごとく涌き、その実皆落ち、その花ひとり栄えて、好色の家には、これをもちて花鳥の使とし、乞食の客はこれをもちて活計の媒となすことあるに至る。故に、半ばは婦人の右となり、大夫の前に進め難し。
(その頃、時代は浮薄なものへと変わり、人は派手さばかりを第一とするようになって、浮薄な歌が雲のように興り、表面的に華やかなものがどんどん出てくるようになり、歌は内実のないものとなり、うわべだけを飾るものとなって、色好みたちは、和歌を、恋心を伝えるための手段とし、経済的に困窮する者たちは、和歌を詠うことで生計のための手段としていたのであった。そのため、和歌は、ほとんど婦人たちのためにあるものとなり、また朝廷の廷臣たちの世界には出すことのできないものとなったのである。)
この箇所、9世紀に入ってからの唐風謳歌時代の和歌のあり方を述べたもので、「真名序」の内容は、ほとんど「仮名序」のそれと同一と言っていいだろう。しかし、一点だけ異なるところに注目しなければならない。それは、「仮名序」では、この時代の歌びとたちについて、「色好みの家」としていたのに対し、「真名序」では、それに加えて「乞食の客」を挙げていることである。
「乞食(きっしょく・こつじき)」とは、『大漢和辞典』にある通り、「食を乞う」という意味の語である。「客」とは、単に人物を指す語として用いられていると思われるが、ただし、この語の持つイメージは悪くはない。「真名序」で用いられる「乞食之客」については、生活に困窮する人、という程度の解釈でいいだろう。貴族社会で言うならば、零落した没落貴族の面々ということになる。
9世紀の和歌事情について、「好色の家」(恋の世界)を中心として、それが詠われていたという認識は、うたが「国風」である以上、妥当としなければならないが、しかし、この「乞食の客」はどうであろう。この時代の和歌を支えていた基軸に、「恋愛」の世界と並んで「没落」あるいは「落魄」の階層の人々を据えるということになるのである。
実は、9世紀の和歌事情を語る物語に、『伊勢物語』がある。『伊勢物語』の成立は、10世紀前半のことで、それは、明確に「一個の作品」として制作された。この作品については、よく「在原業平」の一代記ということが言われるが、実際には業平の実人生よりは時代設定の幅が大きく、平安京遷都まもなくの頃から、ほぼ九世紀末に至る光孝天皇の時代に、少なくとも及んでいる。そして、全125段の各章段の内容は、「恋」が圧倒的に多いものの、それだけではなく、なかに「没落貴族」の落魄の物語(「東下り」もそうである)があることに注目しなければならないのである。
このように考えるとき、『古今和歌集』の平城天皇後の和歌についての歴史認識は、『伊勢物語』のそれと共通のものがあると言ってよく、両者の成立に関わった大きな力は、ほとんど同質のものがあると言わざるを得ない。同一の作者、という見方が当然のこととして浮上して来るのだが、このことは、今は措いておく。