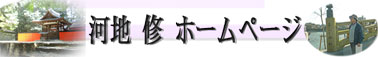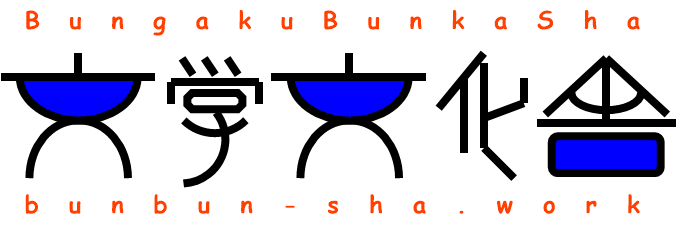講義余話
行平の須磨―貴種流離譚の構図
「女はらから」への「昔男」の求婚を語る『伊勢物語』「初段」は、この物語の主人公が、古代の天皇(英雄時代)を彷彿とさせる「いろごのみ」であることを高らかに宣言するものでもあった(「49.「『伊勢物語』主人公像の造型に関する一考察-初段「昔男」の「垣間見」と「イメージ」をめぐって-」『文学論藻』87号 2013.2.28 」)。そして、その主人公「昔男」が、在原業平であることが判明(二段以降)すると、未遂には終わったものの、入内前の二条后藤原高子を略奪に及ぶという、余りにも激しい「いろごのみ」ぶりが、第六段にて峻烈に表出されたのであった。
このような業平像と比べてみると、はたして、行平は、姉妹二人を同時に「召人」とするような「いろごのみ」にふさわしい人物と言えたかどうか―。むろん、そのかたちは、行平自身の求愛というものではなく、村長である父親からの申し出ではあったが、しかし、〝姉妹〟を同時に寵愛するという構図は、まさに、古代の英雄譚の系譜上にある「いろごのみ」の典型と言うほかはないだろう。
この話が業平であるなら、まさに、うってつけの役どころと言えるのであるが、正三位中納言にまで昇進した史実の行平像からはかけ離れているようにも思われる。あるいは、須磨の行平伝承は、『伊勢物語』に描かれた業平のイメージが、血縁の行平に重なってできあがったものかもわからない。そして、流離の地での娘との婚姻という構図は、いわゆる〝貴種流離譚〟の一典型でもあると言うことができる。
そういった〝貴種流離〟という観点から言えば、『伊勢物語』の「東下り・東国物語」(七~十五段)もそういうものとして読むことができる。物語において、どのような理由かは明示されないが、都の貴公子(業平らしき昔、男)が都を離れ、東国、陸奥へと流離するのである。そして、その中の第十段は、業平らしき「昔、男」と思われる「あてなる人」が、「武蔵国、入間郡、みよしの里」で、「その国にある女」を「よばふ」という話である。「よばふ」とは求婚するということで、「昔、男」が武蔵の国の女に「よばふ」のはいいとして、問題とすべきは、「昔、男」の求婚に対して、女の母親が、積極的にその婚姻を進めたいという旨の歌を、直接、男本人に贈っている点であろう。
物語は、そのくだりを次のように述べている。
父はこと人にあはせむと言ひけるを、母なむ、あてなる人に心つけたりける。父はなほ人にて、母なむ藤原なりける。さてなむ、あてなる人にと思ひける。
(父親は、この男とは別人に縁付けようと言ったのだが、母親は、高貴な人に縁付けようと考えていたのだった。父親は家柄が低い男で、母親は藤原氏の出身なのであった。そこで、高貴な人に娘を、と思ったのであった)
娘の母親は、「あてなる人に心つけたりける」という。「あてなる人」というのは、むろん都から流離してきた貴公子の「昔、男」であり、主人公が、都を遠く離れ流離する構図としては古代の神話に見られる〝貴種流離譚〟と同種と言うことができる。そして、娘の母親が「あてなる人に心つけたりける」とあるように、この母親は、普段から、娘の婚姻相手には「あてなる人」を、と考えていたのである。しかし、「父はこと人にあはせむと言ひける」とあるように、母親の夫である父は、別の男との婚姻を希望していたのだが、母親は、あくまでも、夫とは異なる主張を行ったのである。その理由は、「母なむ藤原なりける」―母親が「藤原氏」の出身であった、ということなのであった。この場合、母が「藤原」であったとはどのようなことを言っているのか。当然のことだが、当時における「藤原」という〝氏〟の存在について、そのイメージのようなものまで考えてみなければなるまい。
言うまでもないことだが、「藤原氏」とは、大化の改新に功績のあった中臣鎌足から始まっている。鎌足の子の不比等の時代に大きく発展して、やがて四家に展開、それぞれの消長を経て、平安時代初期の嵯峨天皇の時代に、北家冬嗣のもと、その隆盛の礎が築かれた。以降、基本的に、北家から姫君が入内し、天皇を産み続けることで、その外戚としての地位をほぼ独占したのである。
このような「藤原氏」の外戚としての栄華の独占体制は、そのまま一族の上、中、下に応じた発展へと結びついたが、当然のことながら、一部の階層を除いては、多くの家が沈淪してゆかざるを得なかったであろう。この武蔵の国に住む「藤原」の母親が、いったいどのような経緯でここに住んでいるのかはわからないが、何らかの事情があって没落していった結果のことに違いない。
しかし、この母親は、流離の貴公子に、自身の藤原としての復活を賭けたのであろう。その構図は、まさに、あの明石入道が、「いかにして都の貴き人にたてまつらむ」と、わが娘を光源氏に差し出そうとした心情と同じものがあると言っていい。