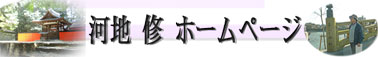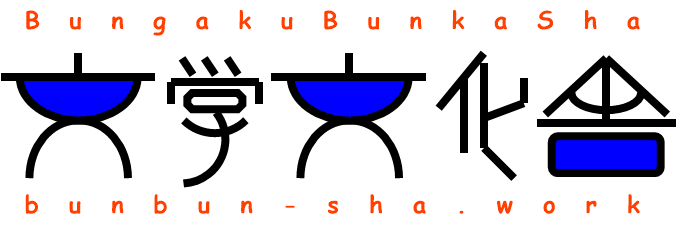講義余話
井上円了のこと―「エンリョーさん」は偉かったか?(2)
護国愛理(ごこくあいり)
このように「えらいエンリョーさん」ではあったが、社会の実際的要請という潮流を読む力はなかったのだろうか―と、気の遠くなるような膨大な「巡講記録(南船北馬集)」に目を落とす度に、思ってしまうのだ。社会が必要とする即戦力の人材養成を、円了は、なぜ思いつかなかったのだろうか。
この疑問に、今明確な答えを見出すことは難しいが、要するに、円了は、学校経営を商売の道具として見ていなかったことだけは確かなことであった。
むろん、円了も、哲学館の経営(学生募集)を考えた。たとえばそれが、「資格」を与えるということであった。官学と同じように、卒業後「中等学校教員資格」が与えられるよう奔走し、そして、ついに実現したが、哲学館の場合、世に言う「哲学館事件(1902)」によって、すぐに潰された。
この「哲学館事件」の後、1905(明治35)年、円了は、学長の職を辞し、大学経営からは遠ざかった。中野に「哲学堂」を開き、自身は、さらに精力的に「巡講」の旅に出た。
要するに、円了は、「志」としての原点に回帰したようであった。この「原点」とは、むろん「哲学」と言っていいが、それは、学問としての「哲学」ではなかった。哲学すること―、すなわち、「理を愛」し、「合理の精神」を持つ、ということであった。
この「愛理(合理)の精神」=「哲学すること」は、“商売”としては扱いにくかったが、しかし、すべてに通じる“真理”ではあった。そのことを端的に述べた言葉が、よく言われている「諸学の基礎は哲学にあり」である。だが、繰り返すが、学生を集める具体的商品としての「魅力」には欠けた。東洋大学は、戦後、総合大学路線に大きく舵を切るまでは、その経営は、きわめて厳しかったのである。
近代日本の歴史において、ほとんどの私学が新時代建設の担い手を養成する「実学の旗」を掲げた中で、円了が独り掲げた「哲学(愛理)の旗」には、“志”の高さとともに、そこには何か“愛嬌”のようなものを感じてしまうが、しかし、円了は、正しかった。
円了の遺した言葉に「護国愛理」というものがある。私が東洋大学に入学した当時の学長は、「国家主義」への連想を嫌って、この言葉の説明として「この場合の“護国”の“国”は“地域社会”と置き換えるように」といつも言っていた。が、むろん、円了は、ごく自然に「国」ということで使用したに過ぎない。
円了が、「国家」や「官」などに魅力を感じるような人物ではなかったことは、生前、すべての叙勲を辞退したことや、「官」よりも「民」だという歌を遺している(写真資料)ことからも、よくわかる。もちろん、円了は「国家主義者」などではなく、あくまでも「民の人」であった。そして、何よりも「国」を愛する人であった。

「官々となる金石の聲よりも民々と鳴く蝉ぞこひしき」
「官々」(官)よりも「民々」(民)が恋しいとする円了の率直な心情が詠まれている。
-東洋大学 千艘秋男教授 提供-
さて、この「護国愛理」という言葉である。つまり、「国」を「護る」ことと「理」を「愛する」こととは、等価であるということを言っている。「理」とは、「哲学」、すなわち「合理、愛理の精神」であることは言うまでもない。
円了は、「理」を愛することこそが「国」を護る道であって、これがなくなれば「国」は滅ぶ、と言ったのである。
円了は大正8年(1919)に亡くなったが、昭和に入り(1928年)、はたして、その言葉どおりの展開となった。
第二次世界大戦(太平洋戦争)当時、物理的に全面戦争などできるはずがないのに、この国は「一億玉砕」を叫んだ。まさに、「国」が「滅ぶ」ところまで行こうとしたのである。国全体が、円了言うところの「理」を忘れた結果であった。あのまま突き進めば、原爆投下の連続によって、文字どおり、この国は「玉砕」することになったに違いない。
考えてもみたまえ、油や鉄鉱石などほとんどないこの国が、世界中のほぼすべてと国交を断絶し、その挙げ句に「全面戦争」を引き起こすなど、無謀と言うよりも、「狂気の沙汰」としか言いようのないことであったのは、それこそ、子供でも分かりそうな「道理」であるが、それが忘れられた。
敗戦によって、多くの政治家・軍人が「戦犯」として罰せられたが、責任を負うべきは、彼らだけではなかったであろう。「哲学」=「愛理の精神」を忘れた、当時の日本という国そのものに対して、その責任は問われるべき性質のものであった。
ともかく、円了は、正しかった。道理としての「哲学」を愛し、当たり前の「理」を持てと言い、それを忘れたときに「国が滅ぶ」と言ったのである。
井上円了は「哲学者」というイメージで語られることが多いが、正確に言えば、「合理、愛理の人」と言うべきであろう。そして、その精神を、「巡講」によって伝道者のごとく終生説き続けたことを思えば、彼は、真の「教育者」でもあった。
昨今、世間の大学のあり方は、「愛理」と言うよりも、「愛利」と言った方がふさわしいような観を呈しているが、むろん円了の「哲学館」の時代同様、私学の学校運営は厳しい。厳しい以上、常に、社会からの要請という観点は忘れてはならないが、しかし、円了が、その生涯を通じて、常に「哲学と愛理の旗」を掲げ続けたことは、何よりも忘れないようにしたい。