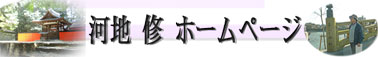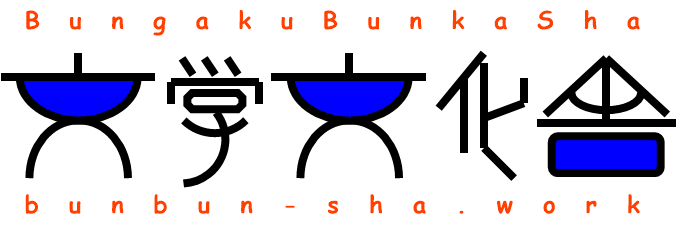-伊勢物語論のための草稿的ノート-
第111回
在原業平生誕1200年―業平を追う
紫式部の評価
紫式部は、『源氏物語』「絵合」巻で、『伊勢物語』と「在原業平」を高く評価した。これは、絶対的評価、とでも言うべき評価で、このことの意味を突き詰めてみたい、という思いが、今もなお、私の中に強くあり続けている。
私がこの「絵合」巻のくだりに注目したのは、昭和50年代のことで、当時は、『伊勢物語』の「成長論」を否定する作業に没頭している時期だった。成長論とは、『伊勢物語』は一回的に成立したものではなく、『古今和歌集』成立(905年)の頃から『拾遺和歌集』成立(1005年~1007年)の頃までのほぼ100年間にわたって不断の成長増益を重ねて出来上がったとする仮説で、片桐洋一氏が提唱された。私どもの立場からすれば、この考え方は「作品」としてある『伊勢物語』を破壊するものに他ならなかった。
成長論が言うところの『伊勢物語』が最終的に成立したとする『拾遺和歌集』成立の頃とは、取りも直さず、紫式部が『源氏物語』を執筆していた時期なのである。その紫式部が執筆した『源氏物語』「絵合」巻で、『伊勢物語』に関して、登場する人物たちが次のような和歌を詠っていることに注目しなければならない。
(平内侍)
「伊勢の海の深き心をたどらずてふりにし跡と波や消つべき」
(伊勢物語が有するところの深い意味を知ろうとせずに、古い物語だと貶していいはずはありません)
(藤壺)
「みるめこそうらふりぬらめ年経にし伊勢をの海士の名をや沈めむ」
(表面的には古い物語のように見えるでしょうが、昔から読まれて来た伊勢物語の名声を貶していいはずはありません)
平内侍は、光源氏が後見する梅壺の女御(斎宮の女御)方の女房で、『伊勢物語』擁護のためにこの歌を詠った。また、藤壺は、『伊勢物語』と争った『正三位』との優劣について、最終的にこの歌で『伊勢物語』に軍配を挙げたのである。
注目すべきは、この時、両者とも、「ふりにし跡」「みるめこそうらふりぬらめ年経にし」と、『伊勢物語』を「古い」としていることである。『伊勢物語』がほぼ100年の間成長を遂げて、紫式部の時代に成立した、などといった成長論の考え方は、この「絵合」巻を読めば、いったいどこから生まれてくるのか、ということになるであろう。
さらに言えば、光源氏が後見する梅壺の女御方の物語は、「いにしへの物語、名高くゆゑある限り」(昔の物語で、評価が高く由緒のあるものばかり)を集めたとあり、そのうちの代表的なものが『竹取物語』と『伊勢物語』なのであった。対峙する弘徽殿(権中納言の娘)方は、「そのころ世にめづらしく、をかしき限り」(当時の新作の物語で、素敵なものばかり)を集めたのであった。古典と新作という対照が図られていることは、言うまでもない。
そして、専門的な見地から言わせてもらうことになるが、「絵合」巻における冷泉帝の御前での絵合の行事は、歴史上の村上天皇の天徳4年(960)3月30日に開催された「天徳内裏歌合」の結構に準拠している(歌合を絵合に変えたのである)。紫式部の歴史認識が厳密を極めていることは周知のとおりであって、つまり、「絵合」巻に示される紫式部の『伊勢物語』に対する見方は、その成立が、村上天皇の天徳四年の時点からして、「古い」物語だという歴史認識なのである。
紫式部は『伊勢物語』と「在原業平」を絶対的に評価する
この「絵合」巻のくだりについて、当時の私は、成長論批判が常に頭にあったものだから、紫式部が、『伊勢物語』を、「伊勢の海の深き心を知らずして」や「伊勢をの海士の名をや沈めむ」などと、繰り返し称賛していることは、あまり正面から取り上げることがなかったように思われる。
こういった称賛の姿勢は、在原業平という人物に対しても見られるもので、そのキーワードとなるものが、前掲の平内侍の言葉にある「業平が名や朽すべき」と藤壺の言葉にある「在五中将の名をばえ朽さじ」の「名」ではないかと思われる。
「名」とは名誉、名声という意味でよかろうと思うが、紫式部が言うところの在原業平の名誉とは何か、このことを具体的に追求しなければならない。ヒントは多いだろう。『源氏物語』の光源氏像そのものがその「名」に相当するであろうし、在原業平の場合は、歴史上実在した人物なのである。
その業平の人物像について、歴史上の資料や詠歌、さらに物語に求めねばならないだろう。本年のテーマの一つとして、在原業平の「名」を追いたいと思う。
→2025年春期 東洋フィロソフィア アカデミー/公開講座
「在原業平生誕1200年『古今和歌集』「業平名歌」誕生の背景とその魅力」
2025.4.26 河地修
一覧へ