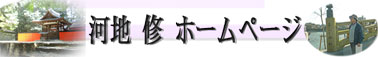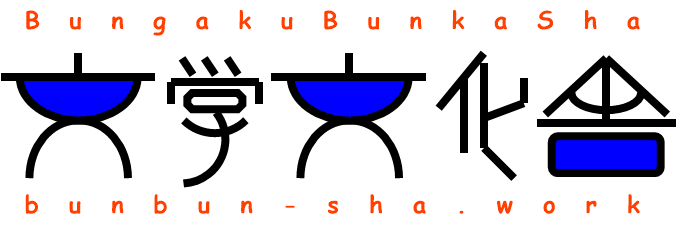講義余話
渡来人、朝鮮半島、そして司馬遼太郎のこと
司馬遼太郎の『街道をゆく』は、もと「週刊朝日」に連載されたものである。連載第一回が昭和四十六(1971)年一月一日号だから、もう三十八年前のことである。
連載第一回目の「楽浪の滋賀」の冒頭で、司馬遼太郎は次のように述べている。
「近江」
というこのあわあわとした国名を口ずさむだけでもう、私には詩がはじまっているほど、この国が好きである。京や大和がモダン墓地のようなコンクリートの風景にコチコチに固められつつあるいま、近江の国はなお、雨の日は雨のふるさとであり、粉雪の降る日は川や湖までが粉雪のふるさとであるよう、においをのこしている。
私は、この冒頭の文章が好きである。世に「司馬史観」と称せられる歴史家、司馬遼太郎が、思わず溜息が出るほどのみごとな文章家であり文学者であることを実感させられるくだりだ。「近江」をふるさとに持つ人が、心底うらやましく思われるほど、この文章は美しい。
司馬遼太郎の「近江」に対するなみなみならぬ思いは、そこに「日本」の原風景を、確かに追い求めることができるという実感からきていることは間違いのないことであろう。そして、そこから感じ取ることのできる原風景こそ、朝鮮半島からの渡来人たちによる風景に他ならなかったのだ。連載第二回目の「湖西の安曇人(あずみびと)」には、冒頭「日本民族はどこからきたのであろう」と始まり、「しかしこの列島の谷間でボウフラのように湧いてでたのではあるまい」とする。昔はともかく、現代、記紀神話に見られる「天孫降臨」のような話をまともに信じる人はいないだろうが、しかし、戦前までこの種の議論はタブーだったのではないかと思われ、昭和四十年代のころでも、この国の起こりについて、冷静に考えようとする人はまだ少なかった。ましてや、まだ朝鮮蔑視の感情が泥に浸み込んだように残っていた時代のことだ。日本という国が、朝鮮半島からの血でかなりの部分ができあがっていた、というような発言をすることは、実に勇気のいることだったに違いない。さらに司馬遼太郎は、友人の金達寿との間に交わされた次のようなエピソードを載せている。
私の友人―といえば先輩にあたる作家に対して失礼だが―金達寿氏と話していたとき、
「日本人の血液の六割以上は朝鮮半島をつたって来たのではないか」
というと、
「九割、いやそれ以上かもしれない」
と、金達寿氏は、三国志のころの将軍のような風貌をほころばせながら笑った。私はそうかもしれないと思いつつも、
「それではみもふたもない」
と、閉口して見せた。
日本民族の大部分が稲作農耕民族としてのDNAを受け継いでいるとするならば、日本民族の祖形としては、むろん「弥生人」の存在を考えねばならないだろう。弥生人は稲作農耕の民であるから、これが日本土着のものでない以上、彼らは渡来人である。この列島には、過去さまざまな渡来人がやってきたと思われるが、その最大のルートは朝鮮半島から対馬、壱岐を伝って北九州へと連なる海上のコースであったに違いない。
古代日本と朝鮮半島―「日本を知る」ことの原点は、今、我々の前に、大きくそして確実なテーマとして存在している。