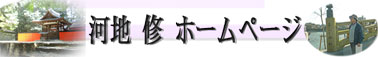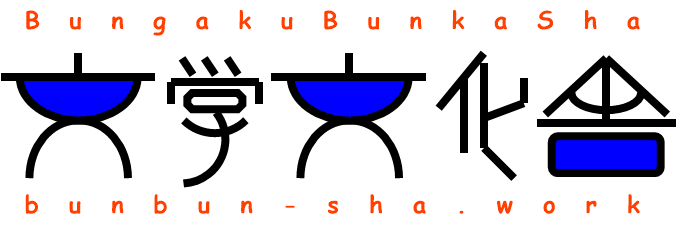講義余話
薬子の変と日本文学文化(一)
藤原式家の天皇―皇位継承の闇
日本史上、「薬子(くすこ)の変」と呼ばれる事件がある。この事件は、大同五年(八一〇)に起こった。昔は「薬子の変」という言い方が主流であったが、最近では「平城太上天皇の変」とも言うようになった。二つの言い方があるということからすれば、薬子と平城太上天皇と、二人の主役がいるということになるのだが、最近の言い方からすると、どうやら主役は、平城太上天皇のようでもある。が、はたしてそうか、というようなことについて考えてみたい。
薬子の変については、たとえば、『日本国語大辞典』は次のように記述している。
平安初期の朝廷内部の政変。藤原薬子は平城天皇の妃の母として天皇の寵愛を受け、兄仲成と共に勢威を振ったが、大同四年(八〇九)天皇が皇太弟嵯峨天皇に譲位すると、翌年薬子と仲成は平城上皇を再び位につけようと画策した。朝廷は、坂上田村麻呂らに命じてこれを防止し、薬子は自殺し、仲成は誅され、上皇の子高岳親王は皇太子を廃され、かわって大伴親王が皇太弟に立てられた。
このように薬子の変とは、譲位した平城上皇を、藤原式家の仲成、さらにその妹の薬子が、再び天皇の地位に就けようとしたという説明なのであるが、これを「平城太上天皇の変」とも言うようになったということは、今ではそこに平城の意思が大きく働いていたということでもあるのであろう。
「太上天皇」とは、皇位を譲位した天皇の称号であり、ありていに言えば、「元天皇」のことである。略して「上皇」とも言うが、住まいは、内裏の外に上皇専用の御所を持った。その邸宅を「後院(ごいん)」とも言ったので、上皇その人の謂いとして「院」とも言ったのである。
平城上皇は、大同四年(八〇九)に、上皇となった。すなわち、皇太弟の神野親王(嵯峨天皇)に譲位したのである。大同元年(八〇六)の即位であったから、天皇としての在位は、わずか三年に過ぎない。何とも短命の天皇ではあった。
平城は、宝亀五年(七七四)、平城京に生まれている。父は、桓武天皇、母は藤原乙牟漏(ふじわらのおとむろ)であった。乙牟漏の父は、藤原式家の良継であったから、母系という観点から言えば、藤原式家の天皇ということになる。平城が生まれた宝亀五年(七七四)は、すでにその前年、平城の父桓武(山部親王)の立太子が行われていた。すなわち、平城は、天皇となるべき人の皇子として生まれたのである。平城のことを考えるときには、父である桓武天皇のことを考えねばならない。
桓武天皇は、父が光仁天皇で、母は高野新笠(たかののにいがさ)と言った。光仁は、称徳女帝(孝謙天皇)の崩御(七七〇年)にともなって、急遽擁立された天皇であった。系図から言えば、天智天皇の孫ではあったが、当時の天皇家の正統な家系ではなかった。光仁は、即位後、皇后である井上(いがみ・いのえ)内親王の生んだ他戸(おさべ)親王を皇太子に立てているので(七七一年)、光仁擁立は、この他戸親王を天皇とするためだと言えなくもない。井上内親王は、聖武天皇の娘であったから、他戸親王は、聖武の孫に当たる。が、すぐに、母の井上内親王と他戸親王とは、粛清された。
宝亀三年(七七二)、皇后である井上内親王は、天皇を呪詛したということで廃され、また他戸親王も廃太子となった。その翌年、宝亀四年(七七三)一月には山部王(後の桓武天皇)の立太子が行われたので、井上内親王と他戸親王の粛清は、山部王の即位を見越してのことであったろう。その山部王は、即位後、自らの皇位継承について、藤原百川の功績が大きいことを述べているから、当時の朝廷の中心勢力であった藤原氏、中でも式家(良継、百川兄弟)の強い意向が働いたものと思われる。つまりは、藤原式家が担いだ天皇であったと言える。
この場合、式家は、かつての藤原不比等のやり方を踏襲した。不比等は、自身の娘宮子を文武天皇の后とし、さらに、宮子所生の首皇子(聖武天皇)の后として宮子の妹の光明子を入内させた。この光明子が孝謙女帝の母であるが、不比等は、光明子を皇后に押し立てた。当時の律令(後宮職員令)では、皇族以外から皇后になることは難しかったが、不比等は初めてそれをやったのである。
この不比等から藤原四家(南家・北家・式家・京家)ができたのはよく知られている。藤原宇合は不比等の第三子であったようだが、式部卿に任ぜられたので、この家を式家と呼ぶのである。宇合の子に、広嗣・良継・百川らがいるが、長子の広嗣が叛乱を起こしたことにより、一時、式家は沈淪した。当然、残された良継や百川は、式家再興のために動いたに違いない。あるいは、その最後の賭けが、桓武天皇の擁立であったのかもしれない。
桓武天皇が即位すると、皇太子には同腹の弟である早良親王が就いた。弟であるから、厳密には「皇太弟」と言ったほうがいいかもしれないが、次の天皇=「日嗣の御子(ひつぎのみこ)」のことを「皇太子」と言うだけのことと考えるならば、それは、皇太子でも皇太弟でもどちらでもいい。
しかし、周知の通り、この早良親王は、天皇として即位することはなかった。すなわち、延暦四年(七八五)廃太子となったのである。
その理由は、桓武の腹心であった「造長岡宮使」藤原種継の暗殺に関わって、その影の首謀者と断定されたことであった。種継は、桓武天皇誕生の最大の功労者であった藤原百川の後を継ぐ式家の中心人物であったから、桓武は激怒した。そして、直接の実行犯に大伴継人らがいたため、すでに死亡していたが、大伴氏の長老であった大伴家持が関わったとされたのである。当時家持は、征東将軍として陸奥に遠征し、すでに事件の一ヶ月前にはこの世にいなかったが、家持は皇太弟の早良親王と関係が深かった。おそらくは、ただそれだけのことで、早良親王は逮捕された。早良は、自身の無実を訴えて、絶食死するに及ぶが、この壮絶な死と、後の早良親王の怨霊に対する桓武の怖れぶりからすれば、早良は冤罪であったとする後世の判断は正しいのではないかと思われる。時の皇太弟は、同腹の兄の天皇によって殺されたのである。
桓武天皇が、奈良仏教を憎悪したであろうことは容易に想像できる。それは、国家を預かる天皇としては、当然のことであった。この先また、いつ道鏡のような仏教指導者が出てこないとも限らず、さらに言えば、国家の財を食い尽くした大本が奈良仏教であり、その中心に位置する寺が東大寺であったから、桓武の東大寺への憎悪は深かったのではないか。早良親王は、この東大寺との関係が濃密だったのである。
桓武としては、当然のことだが、自身の次の天皇のことが気になったに違いない。すなわち、奈良仏教に敢然とした姿勢を示す天皇でなければならなかった。その点で、早良は、あるいは、脆弱だったと言っていいかもしれない。が、しかし、それだけのことではなかったように思われる。
それは、次の天皇が「皇太弟」か「皇太子」か、という問題であり、もっと砕いて言えば、「弟」か「子」かという、あまりにも人間くさい問題であったとも言える。
この問題、桓武は、対奈良仏教という、天皇としての公的判断以外に、一人の父親としての私情を絡ませたと思われる。それは、かつて、天智天皇が、皇太弟(大海人皇子)を廃し、子である大友皇子(弘文天皇)を皇位に就けようとした壬申の乱(六七二年)の構図と同じものがあると言っていい。一人の父親でもある桓武は、壬申の乱から一一三年後の平安京において、天智と同じく、再び父としての「情」に苦しみ、かつ、その「闇」に足を踏み入れたものと思われる。
七八五年の平城の立太子は、その年齢で言えば十一歳の時であったから、おそらく、この事件の隠された真相については、疑問に思うようなことはなかったであろう。ただ、「日嗣の御子」であった叔父の早良親王が逮捕幽閉され、さらに無実を訴えて絶食死に至ったことは、それがどのようなかたちで伝えられたにせよ、少年の心に衝撃を与えたことは動かないであろう。平城にとって、この二十四歳年上の叔父の印象は、出家までした学究僧特有の心穏やかなる人というものであっただろうから、種継暗殺の黒幕といったような印象とは、まったく相容れないものがあったに違いない。
そして、やがてその早良が、強烈な怨霊となって父桓武を苦しめるようになってからは、平城自身も、その苦しみを共有するしかなかった。なぜなら、父桓武は自分を皇位に就けるために、心優しき叔父を殺したのではないかという責めを、平城自身、その心に向って発し続けることになったはずだからである。
当然のことながら、このことは、生涯平城の心を苦しめたように思われる。やがて、平城が、自分の妃の母である薬子にのめり込むようにすがってゆくのも、早くに乙牟漏を失うという母の愛への渇望という側面があったにせよ、おのれ一人では支えきれぬ心の暗部の存在があったと思わざるを得ない。
平城天皇の在位がわずか三年で終わったのは、そういう心の負荷が重すぎたということもあったのであろう。さらに、今も昔も変わらないが、そういう傷心は、ついに「ふるさと」への帰郷を渇望するものでもあった。平城は、譲位してすぐに、奈良へ帰ったのであった。